更新日:2025.03.05
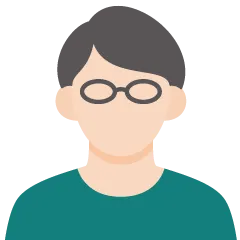
Aさん/50代男性
離婚成立/妻の自宅からの退去
職業
会社員
婚姻期間
15年
(うち別居期間4年)
離婚の種類
裁判離婚
(訴訟で和解、調停に代わる審判)
子ども
あり
依頼者は、精神不安定な妻と一緒に過ごすことが困難となり、当時小学生だった長男を連れて別居しました。
依頼者は、早期の離婚を希望し、受任時には、既に2度離婚調停を申し立てていましたが、いずれも妻に離婚を拒否され、別居が継続していました。
そのため、弊所が依頼を受けて、離婚訴訟を提起することとなりました。

家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。


裁判所において、財産分与に関する処分の審判の申立人が給付を受けるべき権利者となるように財産分与の内容を定めるか、そうでなければ当該審判の申立てを却下しなければならないものと解すべき理由はなく、相手方が給付を受けるべき権利者となるような財産分与を定めることも可能であると解される。

離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相談の流れはこちら
弁護士 渡邊 佳帆

裁判所において、婚姻費用と養育費は、標準算定方式・算定表に基づいて算定されます。
標準算定方式とは、平成15年に東京・大阪の裁判官が提案した、家庭裁判所の実務において採用されてきた方式を基本としつつ、統計資料等の結果に基づき、一定割合や指数を用いて婚姻費用・養育費を算定する簡易な計算方式です。算定表は、その方式に基づく婚姻費用・養育費の額を表にしたものです。標準算定方式・算定表の登場により、婚姻費用と養育費の算定が迅速かつ公平にできるようになりました。
この標準算定方式は社会実態の変化を受けて令和元年に見直されましたが、基本的な理念や考え方は変わっていません。
標準算定方式における婚姻費用・養育費は、統計上の平均的な家庭の生活費を想定して算定されています。教育費も例にもれません。標準算定方式においては、14歳以下の子がいる場合は、年額13万1302円(公立中学校学費)が、15歳以上の子がいる場合は、年額25万9342円(公立高校学費)が学校教育費として考慮されています。そのため、子が私立の学校に通っている場合や、大学に通っている場合は、別途計算が必要になります。
一方で、習い事代は標準算定方式においては考慮されていません。そのため、標準算定方式に基づく婚姻費用・養育費に加算して請求ができます。しかし、無制限に支払義務が認められるというわけではありません。
まず、婚姻費用や養育費を支払う側(義務者、と言います。)の承諾があった場合は、義務者は習い事代を支払う必要があります。支払う額は全額とは限らず、子を監護し、婚姻費用や養育費の支払いを受ける側(権利者、と言います。)と義務者の収入比で考える場合や、折半する場合があります。
義務者、権利者及び子が一緒に住んでいたころからその習い事をしていた場合は、その習い事について義務者の承諾があったとみなされることがほとんどです。義務者と権利者・子が別居した後に習い事を始めた場合でも、義務者が承諾すれば習い事代の負担を求めることができます。
ただ、承諾があったといっても、費用の支払を求めることができるのは、義務者が通常想定し得る範囲に限ります。たとえば、子が成長しても権利者が大会等に付き添う場合の付添費や、家でも習い事の練習ができるように家を改装した場合の改装代等は、必要性が乏しく、義務者が当初想定していたものでもないのであれば、支払を求めることは難しいと言えます。
仮に義務者の承諾がなかったとしても、当該習い事の必要性や、義務者と権利者の経済状況を鑑みて、義務者に負担させることが相当と判断される場合もあります。
標準算定方式は、子の年齢と数、権利者と義務者の年収さえわかれば、誰でも迅速に婚姻費用・養育費が計算できる画期的な仕組みです。しかし、あくまで「標準」の婚姻費用・養育費の算定方式を定めたものであるため、各家庭の個別事情に応じ別途修正が必要です。
修正事情として考慮していい事情と考慮できない事情の区別、考慮する際の方法等は、専門家であっても様々な文献・裁判例にあたって判断する必要がある複雑なものです。中には、複数の考慮方法があるため、実際の協議、調停や訴訟において議論になるものもあります。
現在は、様々なサイトで簡単に婚姻費用・養育費が算定できますが、それらは標準算定方式に基づくものであると言えるでしょう。ご家庭の個別事情を考慮に入れたい場合は、別途検討が必要になります。専門家にご相談ください。
弁護士 田中 優征

離婚の相談を受ける中で、配偶者のモラハラが原因で、離婚したいという話を聞くことがあります。
モラハラという言葉が一般化し、法律上は定義も明確にされていませんので、何をもって「モラハラ」とするかは一様ではありませんが、
例えば、「暴力は振るわず、言葉や態度で嫌がらせをし、いじめること。」(goo辞書)等のように表現されることが多いでしょう。
それでは、モラハラは離婚の原因となるのでしょうか。
まず、前提として、離婚の原因について確認しておきます。
離婚の原因は、民法770条1項各号に規定があります。
内容は以下のとおりです。
各号のいずれかに該当する場合には、離婚訴訟において離婚が認められることになります。
モラハラは、1号から4号に該当する事情にはなりませんので、5号に該当するかどうかが問題になります。
5号は1号から4号を包括する一般的な規定と考えられています。
5号の婚姻関係を継続し難い重大な事由がある場合について、日本の裁判所は破綻主義、すなわち、婚姻関係が破綻している場合には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると判断する立場であると理解されています。
したがって、明確な基準があるわけではありませんので、モラハラが離婚原因、すなわち婚姻関係の破綻を示す事情になるかどうかについては、程度問題であり、事案によることになります。
ここでは、参考として、いわゆるモラハラ的な言動を詳細に認定し、離婚原因があると判断した裁判例を紹介します。
元妻である原告が、元夫の被告に対し、被告のモラルハラスメント行為によって離婚を余儀なくされたと主張して、慰謝料の支払いを求めた事案です(本稿と直接の関連がない請求については省略します)。
裁判所は、被告の婚姻後の原告に対する一連の暴言がいわゆるモラルハラスメント行為に当たり、原告の人格権を侵害するものであることは明らかとしたうえで、被告が原告との交際開始時においては婚姻継続中であったこと、前妻との子がいることを秘匿し、婚姻後も自らの婚姻歴について正しく説明していなかったこととあいまって、婚姻関係を破綻させる要因になった(すなわち、離婚の原因となった)と判示し、慰謝料として200万円の支払いを命じました。
なお、被告による自己の発言を正当化する主張については、自信の言葉が相手を傷つける暴力的なものであるとの自覚を欠いているためであるとして排斥しています。
上記の裁判例では、被告による一連の行為が、メッセージアプリ上等に残されており、詳細に検討することができた結果、被告の行為の程度が社会的に見て相当程度問題のあるものであったことから、一連のモラハラ行為やその他の事情も含めて考慮すると、被告の行為が離婚の原因となったという認定をされたものと考えられます。
このように考えると、モラハラが離婚原因に該当すると主張する際には、以下の2点に留意する必要があるでしょう。
① 訴訟において、モラハラ行為があったことの立証ができるかどうか。
モラハラ行為があったという主張をする場合には、モラハラ行為の証拠を提出し、それによってモラハラ行為があったと認定される可能性があります。
具体的な立証の方法としては、メールやLINE等のやり取り、録音などを提出することになります。
しかし、上記の裁判例のように、モラハラ行為の膨大な記録が、詳細に残っている例ということは多くないでしょうから、立証が困難なことも多いと思われます。
① モラハラ行為によって、婚姻関係が破綻しているとまでいえるかどうか。
最初に述べた通り、モラハラという言葉はかなり多義的な言葉です。
夫婦関係が良好ではなく、離婚を検討するような状況になっている夫婦においては、少なからずモラハラ的な言動が生じているといえるでしょう。
あまりに簡単に離婚が認められてしまうと、婚姻制度そのものが揺らぎかねませんから、その(一連の)モラハラ行為をもって法律上離婚を認めるべき程度に婚姻関係を破綻に陥らせたというには、高いハードルがあると考えられます。
上記のような問題点から、配偶者のモラハラ行為によって離婚を決意した場合であっても、その程度や立証可能性の程度に応じて、別居期間やその他の事情をも含め、総合的にみて離婚原因があるという構成をする必要がある場合がほとんどだと思われます。実際、上記裁判例においても、モラルハラスメント行為以外の事情も判断の理由として挙げています。
しかし、モラハラ行為の主張・立証が無駄になるというわけでもありません。どのような経緯で別居に至ったかということも重要な事情となりますし、離婚原因があるかどうかは総合的にみて判断されるからです。
離婚についてお考えの方は、一度ご相談ください。
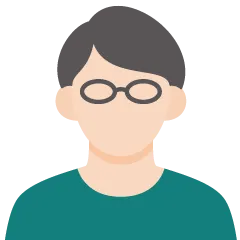
財産分与について合意し離婚調停成立、婚姻費用調停成立
さらに詳しく見る▶
更新日:2025.01.15
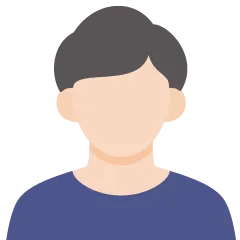
Aさん/40代男性
離婚成立/和解金取得/一般的な水準よりかなり低額な婚姻費用負担
職業
その他専門職
婚姻期間
3年(うち別居期間1年)
離婚の種類
裁判離婚
子ども
なし
夫のAさんは、不倫をした妻との生活に耐え切れず、別居をしました。すると妻がいきなり婚姻費用分担の調停を申し立ててきました。
Aさんは仕事が忙しく、裁判所に行くことが困難であり、またいきなりの婚姻費用分担請求に対して対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚の原因として民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき。」が挙げられています。不貞行為、浮気、不倫と色々な表現方法がありますが、要するに配偶者以外の異性と性行為またはそれに類する行為をすることを指します。
このような不貞行為があれば、通常であれば不貞行為をした側は離婚すること自体には応じることが多いとは思われます。
しかし、中には自ら不貞行為をしていても離婚を拒否する人もいますので、そのような場合には時間がかかることもあります。
今回の事件のポイントとしては、以下が挙げられます。
不貞行為は民法でも離婚の原因として挙げられていますので、それ以外に特段の事情がなければ、不貞行為をされた側は離婚を請求して認められる可能性が高いと言えます。
しかし、だからといって不貞行為をした側が必ずしも離婚に応じるとは限りません。
このような場合には、必ずしも交渉で解決することにこだわらず、離婚調停を申立て、離婚調停でも合意ができなければ離婚調停を速やかに不成立とし、できるだけ早期に離婚訴訟を提起するといった、素早い法的手続の行使が重要になってくると考えられます。

【判旨】①未成熟の二子に対する養育費の負担については,別居の責任が夫婦のどちらにあるかにかかわらず,子供が親と同程度の生活を保持するための費用を分担する義務があるものであるが,別居につき責任を有する配偶者である妻自身の生活費については,夫の分担義務を定めることは相当でない。 ②別居後間もない時期で,無収入の妻がみずから稼得する途を探求するなど生活の建直しに少なくとも必要かつ相当な期間については,妻自身の生活費の分担として,生活保護法による生活扶助基準月額金3万8270円の割合の金員は夫に負担させるのが相当である。 ③それ以降の期間については,妻が収入を得るに至った昭和58年8月以降,妻自身の生活費の分担を夫に求める申立の部分は認めることができない。 (名古屋高裁金沢支部決定昭和59年2月13日・判タ528号301頁)

妻と相手の男性の浮気が証拠上はっきりしているケースで、夫婦の離婚の責任がどちらにあるかということと子どもの養育費については無関係なので、有責配偶者から請求することもできるが、妻自身の生活費についてはそのまま請求を認めるのは相当ではないという判断です。
ただし、妻自身の生活費についても一切認めないというわけではなく、別居後間もない期間で生活を立て直すために必要な期間中は、生活保護費相当額の請求をすることはできるという判断をしています。

【判旨】①抗告人と相手方が別居するに至った直接の原因が本件暴力行為であることは明らかであり、抗告人と相手方との間においては、別居の開始以降、婚姻関係を巡る相当に激しい紛争が続いているということができるところ、前記認定事実によれば、抗告人と相手方の婚姻関係は、同居中から円満とはいえない状態であったことがうかがわれるが、別居に至るほどの亀裂が生じていたとは認められず、本件暴力行為が原因となって一挙に溝が深まり、別居の継続に伴って不和が深刻化したと認められる。 ②抗告人と相手方の別居の直接の原因は本件暴力行為であるが、この本件暴力行為による別居の開始を契機として抗告人と相手方との婚姻関係が一挙に悪化し、別居の継続に伴って不和が深刻化しているとみられる。そして、本件暴力行為から別居に至る抗告人と相手方の婚姻関係の悪化の経過の根底には、相手方の長男に対する暴力とこれによる長男の心身への深刻な影響が存在するのであって、このことに鑑みれば、必ずしも相手方が抗告人に対して直接に婚姻関係を損ねるような行為に及んだものではない面があるが、別居と婚姻関係の深刻な悪化については、相手方の責任によるところが極めて大きいというべきである。 ③別居及び婚姻関係の悪化について上記のような極めて大きな責任があると認められる相手方が、抗告人に対し、その生活水準を抗告人と同程度に保持することを求めて婚姻費用の分担を請求することは、信義に反し、又は権利の濫用として許されないというべきである。(東京高裁平成31年1月31日決定 判タ 1471号33頁)

このケースでは、妻の子どもに対する暴力行為が夫婦関係を悪化させた原因であり、妻にも収入があり、かつ、夫が別居後に妻の住居費を負担していること、夫が子どもの生活費や学費を負担していることなどから、妻からの婚姻費用の請求を認めませんでした。
原則として、婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費を分担する義務に基づいて請求されます。したがって、有責配偶者(不倫や暴力など離婚原因を作った側)であっても婚姻費用を請求する権利が完全に否定されるわけではありません。
過去の判例からしても、子どもの有無や各々の経済状況など個別の事情が大きく影響していることが分かります。もし有責配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられてしまった場合は、適切な証拠を揃え、弁護士の助言を受けながら対応することが重要です。

夫婦は、生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用について、生活費を分担します。この一切の費用を「婚姻費用」と言います。
婚姻費用分担の始期は、婚姻費用分担の請求時とされています。この「請求時」とは、「婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した時点(宇都宮家審令和2年11月30日)」とされます。婚姻費用分担調停の申立ては婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明したことにあたります。
分担を求める意思を確定的に表明した時点が始期になる理由には、別居時から婚姻費用分担金の支払を認めることができるとすると、期間が長い場合、高額となり、婚姻費用分担の義務者(支払う側)にとって酷になること、これに対して、婚姻費用分担の権利者(支払われる側)としては、婚姻費用分担金の支払を求めるまでは、一応の生活をしていたと考えられることが挙げられます(福岡家審平成30年7月18日参照)。
婚姻費用分担の始期以降に支払われなかった分の婚姻費用は、調停等で婚姻費用の分担額が決まった際に、遡って請求ができます。
しかし、もし婚姻費用を払う側が、払われる側の生活費等を負担していれば、それは既払い分の婚姻費用として扱われます。たとえば、婚姻費用を支払う側の口座から払われる側の光熱費や携帯料金の引落しがあったり、支払われる側が支払う側のクレジットカードを使用していたりすると、その分は既払い分の婚姻費用として扱われる可能性があります。
夫婦の一方が別居し、婚姻費用の分担を請求した後で、請求された側(支払う側)の口座から、同居中の生活費のためのクレジットカードの引落しがあった場合、婚姻費用の既払い分として認められるのでしょうか。
この点につき、東京高決令和5年4月20日は、「利用年月日はいずれも別居開始前」のクレジットカード引落しにかかる負担分は、引落しが別居日以降でも、「別居開始後の相手方(筆者注:婚姻費用の分担を請求した側)世帯の生活費とはいえず、婚姻費用の既払金とは認められない。」と判断しました。
一方で、別居後の婚姻費用の分担を請求した側の利用にかかる引き落としについては、「別居開始後の相手方世帯における生活費といえるものであるから、婚姻費用の既払金と認められる。」としています。
婚姻費用分担調停を申し立てられた後も、数か月にわたって婚姻費用が支払われないこともありますが、その間は、未払い分の婚姻費用が蓄積されているといえます。その分は、原則、調停成立時に支払わなければなりません。
そのため、既払い分の婚姻費用にあたる出金の有無の確認は、婚姻費用分担を請求する側にとっても、される側にとっても重要になります。
いずれにせよ、婚姻費用の分担を請求する側は、すぐに調停の申立てを検討することが一番です。

離婚後、取り決め通りに養育費はきちんと払ってきました。
しかし、
① 病気をして会社を休職しています
② 転職して、再就職したら収入が減りました
③ 再婚して、再婚相手との間に子どもが産まれました
④ 再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組しました
⑤ 養育費を受け取る側の収入が増えました
⑥ 養育費を受け取る側が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をしました
養育費を支払う側、受け取る側、どちらも事情が変化することはあるでしょう。
養育費を支払う側は事情の変化に伴い、養育費の減額を希望する相談です。
またその逆で、養育費を受け取る側は養育費の増額を希望することもあるでしょう。
取り決めをした時には予測できなかった事情の変更が生じたとき、養育費の減額(増額)を請求することができる場合があります。
まず、元配偶者と話し合いましょう
話し合っても応じてもらえないときは、
裁判所へ養育費減額の調停を申し立てましょう
いずれにしても、あくまでも話し合いの手続きですので、成立には当事者双方の合意が必要です。
詳しくは こちら をご参照ください。

夫婦が協議をして離婚する場合、離婚をすることや離婚の各種条件について 合意した内容を公正証書として作成しておくことがあります。
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、 公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
(日本公証人連合会HP https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01)
公正証書として残しておくことのメリットはいくつかありますが、最も特筆すべき点は、金銭の支払いについて、直ちに強制執行に服する旨の文言(強制執行認諾文言)がある場合、公正証書が債務名義となり (執行証書といわれています。)、強制執行が容易になることです。
離婚に際しては、養育費や慰謝料・財産分与など、金銭的支払についての合意をすることが多いため、協議離婚の場合には公正証書を作成することが重要視されています。
金銭的給付については、公正証書を作成しておけば、強制執行をすることができるといいますが、 その実際上の要件はどのようなものでしょうか。
強制執行手続をするには、以下の3つが必要になります。
強制執行のもととなる文書のことです。
民事執行法22条に列挙されており、裁判所の判決がその代表例です。
執行証書もこれに該当します。
債務名義が債務者のもとに送達、すなわち適式な手続で届けられていることが必要になります。
執行証書の場合は、債務者本人が公証役場に来ている場合には、その場で交付して送達するか、
代理人などが来ている場合には別途郵送での送達手続をする必要があります。
債務名義に対し、それぞれ判決文であれば裁判所書記官、執行証書であれば公証人が、
強制執行可能であることを確認し、その旨の記載を債務名義に付記することをいいます。
執行証書では、その公正証書を作成した公証役場に公正証書の正本を提出し、
公証人に執行文を付与してもらうことになります。
③の執行文については、いくつか種類があります。
請求について特段の条件が付されていない場合には、公証役場に公正証書の正本を提出して執行文の付与を受ければ足ります。
この場合の執行文を単純執行文と呼ぶことがあります。
これに対し、請求が何らかの事実の到来を条件にしている場合があります。
この場合の執行文は、事実到来執行文や条件成就執行文等と呼ばれています(以下は、事実到来執行文に統一します)。
事実到来執行文の付与を受けるためには、公証人に対して、その条件になっている事実が到来していることを示す文書を示す必要があります(民事執行法27条1項)。
そして、事実到来執行文の場合、執行文及び公証人に提出した文書の謄本を債務者に送達されていなければ、強制執行をすることができません(民事執行法29条後段)。
ここで、離婚届を提出する前に、公正証書において金銭的支払いの取り決めをする場合、 その支払いは離婚の届出・受理を条件としているかどうか、考えてみたいと思います。
例えば、財産分与は、法律上は、離婚して初めて権利が発生するものとされていますし、養育費は、 離婚以前は夫婦間の生活費負担と合わせて婚姻費用と呼ばれるので、離婚してから初めて権利が発生するものと考えられます。
そうすると、これらは離婚を条件として発生するものとして、強制執行をする前提として、事実到来執行文の付与が必要になるようにも思えます。
この点につき、結論からいえば、
当事者がどのような意思でその合意をしたかを、公正証書の文言によって合理的に解釈するため、個別の事案によって異なる
ということになります。
この点について、2つの東京高裁の裁判例を紹介します。
なお、いずれも詳細に紹介するとかなり長文となってしまうため、概略の説明にとどめます。
東京高裁平成28年1月7日決定は、事案としては、公正証書の冒頭に、「…離婚することに合意し、離婚に伴う子の…慰謝料…の支払いなどについて以下の通り合意をした」との記載が、 慰謝料について、「離婚による慰謝料として金850万円の支払義務があることを認め、…支払う」との記載がそれぞれあったというもので、 原審は事実到来執行文が必要としていましたが、高裁は、当事者の合理的意思解釈として、 離婚の成立を前提としない支払義務を定めたものとして単純執行文で足りると判断しました。
これに対し、東京高裁令和3年4月7日決定は、公正証書の記載は「A(注:夫婦たる双方当事者の子ども)の養育費として、 平成19年5月からAが満20歳に達する日の属する月まで1か月金〇万円の支払義務があることを認め、 これを翌月5日限り支払う」となっていた事案で、離婚届の成立を前提として定められたと解するのが当事者の合理的意思だとして事実到来執行文の付与が必要であると判断しました。
このように、個別の事案によって、事実到来執行文が必要か、単純執行文で足りるのかが異なる場合があります。
さて、金銭の支払いを確保する強制執行手続においては、その目的となる財産によって手続が異なりますが、例えば債務者の預金を差し押さえる手続は、債権執行という手続になります。
債権執行においては、事前に債務者に強制執行が行われることが通知されてしまうと、容易に財産を隠匿することができるため、
債務者への通知なく差押えをすることができることになっています(民事執行法145条2項)。
しかし、上記で説明したように、事実到来執行文が必要となると、執行の前提として、執行文及び離婚の成立という事実が到来したことを示す文書(離婚後の戸籍謄本等)
を債務者に送達しなければならず、強制執行の準備をしていることを察知されてしまいます。
この場合の執行文は、事実到来執行文や条件成就執行文等と呼ばれています(以下は、事実到来執行文に統一します)。そうすると、いざ強制執行をする段階で、事実到来執行文が必要になってしまったため、預金を隠匿されるということが生じる可能性もあります。
また、単純に事実到来執行文の付与は単純執行文の付与よりも手間がかかりますので、スムーズな手続進行が阻害されることになると思われます。
この問題の対応策としては、離婚成立を前提とした条項にする場合には、公正証書の作成後、離婚が成立した段階で早期に事実到来執行文の付与を受けておくことが考えられます。
また、公正証書の作成時に、金銭的支払いが、離婚成立を前提としていないことを条項上明確にしておくことも考えられます。
いずれにしても、金銭的支払いを受ける方の当事者は、公正証書の文言についても公証人と協議する等して調整しておく必要がありそうです。
いずれにしても、金銭的支払いを受ける方の当事者は、公正証書の文言についても公証人と協議する等して調整しておく必要がありそうです。本稿では、離婚時に作成する公正証書と強制執行の要件である執行文との関係について述べました。
離婚時に公正証書を作成する目的の一つとして、金銭が約束通り支払われない場合に強制執行をすることが可能な点がありますので、強制執行手続についても検討しておく必要があります。
なお、本稿で述べた内容も含め、どの程度具体的に強制執行を想定して準備しておくべきかどうかは個別の事情によるところもあると思われます。
離婚についてお困りの方は一度ご相談ください。
令和6年12月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年12月18日に名古屋地方裁判所にて損害賠償等請求事件 について民事訴訟を提起しました。
令和6年12月12日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。
令和6年12月20日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年12月18日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年12月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。
令和6年12月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。
令和6年11月12日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
令和6年11月28日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和6年11月28日に裁判所にて損害賠償等請求事件について判決が出ました。
令和6年11月30日に面会交流調停事件の裁判外の和解が成立しました。
令和6年10月17日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年10月17日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年10月2日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について和解が成立ました。
令和6年10月2日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について和解が成立ました。
令和6年10月9日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。
令和6年10月22日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年10月30日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年10月30日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年10月28日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年10月31日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年9月5日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停事件 について調停が成立しました。
令和6年9月18日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年9月20日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年9月27日に名古屋家庭裁判所にて面会交流審判事件 について審判が出ました。
令和6年9月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年9月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年9月20日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について判決が確定しました。
令和6年8月9日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年8月15日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年8月8日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚等請求事件 について審判が出ました。
令和6年8月26日に名古屋家庭裁判所豊橋支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月16日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて面会交流調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月16日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月26日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月26日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月7日に大阪家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月26日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月26日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月8日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年8月30日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について家事調停を判決が出ました。
令和6年7月2日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整調停事件 について調停が成立しました。
令和6年7月8日に名古屋地方裁判所にて損害賠償請求事件 について民事訴訟を提起しました。
令和6年7月5日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年7月5日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年7月22日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年7月16日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年7月16日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年7月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事審判を申立てました。
令和6年7月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年7月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用減額調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年7月31日に名古屋家庭裁判所第一支部にて夫婦関係調整(離婚)事件 について調停が成立しました。
令和6年6月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事審判を申立てました。
令和6年6月5日に名古屋家庭裁判所にて子の氏の変更許可審判申立事件について家事審判を申立てました。
令和6年6月7日に名古屋家庭裁判所にて子の氏の変更許可審判申立事件について審判が出ました。
令和6年6月11日に名古屋家庭裁判所にて子の氏の変更許可審判申立事件について審判が出ました。
令和6年6月15日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件について審判が確定しました。
令和6年6月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事審判を申立てました。
令和6年5月7日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月7日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月13日に東京家庭裁判所立川支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について審判が出ました。
令和6年5月13日に東京家庭裁判所立川支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について審判が出ました。
令和6年5月17日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月21日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年5月21日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年5月27日に名古屋家庭裁判所半田支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月27日に名古屋家庭裁判所半田支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月28日に名古屋家庭裁判所にて子の氏の変更許可審判申立事件 について家事審判を申立てました。
令和6年5月28日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月29日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年5月31日に名古屋家庭裁判所にて離婚請求事件 について調停に代わる審判が出ました。
令和6年5月31日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年5月31日に名古屋家庭裁判所一宮支部にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。
令和6年3月18日に最高裁判所で強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。
令和6年3月19日に岐阜家庭裁判所で離婚等請求事件について審判が出ました。
令和6年3月27日に名古屋家庭裁判所半田支部で間接強制申立事件について決定が出ました。
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年2月2日に名古屋家庭裁判所半田支部で引渡実施申立事件について申立てしました。
令和6年2月5日に名古屋高等裁判所で抗告許可申立事件について決定が出ました。
令和6年2月5日に名古屋家庭裁判所で婚姻費用分担調停事件について決定が出ました。
令和6年2月6日に名古屋家庭裁判所で夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
令和6年2月6日に名古屋家庭裁判所岡崎支部で面会交流調停申立事件について審判が出ました。
令和6年2月14日に名古屋家庭裁判所で離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
令和6年2月20日に名古屋家庭裁判所半田支部で間接強制申立事件について強制執行を申立てました。
令和6年2月28日に名古屋家庭裁判所で夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。
令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。
令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。
令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)