
年金分割の請求を行うことができるのは、離婚成立日の翌日から2年以内です。また、相手が死亡した場合、死亡日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。
協議離婚後に、年金分割の調停・審判を申し立てる場合がありますのが、その際に、離婚成立日から2年以内に申立てをしていても、調停成立や審判確定に時間がかかり、期限の2年をすぎてしまう場合があります。
その場合には、救済措置として特例があります。
相手が死亡した場合、死亡日から起算して1か月を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。相手の合意があっても、離婚後に年金分割の審判をもらっていても、年金分割の請求はできなくなります。
判例(東京地判平26・7・11(平成25年(行ウ)第114号)では、夫の死亡を知らなかったとして、年金分割請求を却下する旨の処分の取り消しを求めた事案について、年金分割の請求は不適法としています。
そのため、年金分割については、すぐにでも年金事務所で手続きを行うことが大切です。
参考:Q&A財産分与と離婚時年金分割の法律実務 発行民事法務研究会 著小島妙子

妻Aさん 依頼者様
夫Bさん
Aさんは、Bさんと離婚し、おおよその財産分与の額も決まっていましたが、支払い時期を数年後に設定しなければならなかったため、公正証書の作成をしたいということで、弊所にご相談に来られました。
おおよその内容は既に決まっているということで、弊所で離婚公正証書作成プランにて受任し、公正証書作成のお手伝いをさせていただきました。
離婚時に財産分与の額を一定額に定めることができないため、Aさんと相談し、強制執行との関係も加味しながら、文案を作成しました。具体的には、固定部分の記載と変動部分の記載に分け、固定部分については強制執行可能な形にしておきながら、変動部分についても計算方法を明示することで、任意に支払われる場合にも齟齬が出ないようにしました。
その後、公証役場と連携し、文案を細かく確認しながら、公正証書の文案を確定し、作成に至りました。
公正証書は、強制執行を可能にするという点で非常に有用なものですが、支払期日を先に設定しなければならない場合や、現時点で財産分与の金額が決まっていない場合等は、強制執行可能かどうかについて気を配る必要があります。
内容によって気にしなければならない点が異なりますので、注意が必要です。
2か月

妻Aさん 50代 依頼者様
夫Bさん 50代
妻Aさんは、夫Bさんと主に財産分与の支払い方法についてもめているとのことで、弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは一括払いを、Bさんは分割払いを希望しているとのことでした。
まず、Aさんと一緒に夫婦の財産を整理し直しました。
その結果、確かにすぐには換価できない財産も多く、一括での支払いは少し夫側の負担が大きいことが分かりました。
そのため、夫と交渉を行い、分割払いに応じることを条件に、財産分与金の総額を増やすとともに、財産分与金の支払いを担保するため、
夫が所有する不動産に抵当権を設定することの合意を取り付けました。
財産分与金を分割払いにする場合、支払いに不安を感じる方はたくさんいらっしゃると思います。
離婚事件において、抵当権を設定することは比較的少ないとは思いますが、
本件は、財産分与金の支払総額が高かったということと、担保を設定することができる不動産があったということから、抵当権を設定するといった方法を取りました。
抵当権の設定までスムーズに行うことができたのは、複数の士業がいる弊所の強みだと思います。

Aさん(元夫)
元配偶者(元妻)
Aさんは、離婚して母親が親権者になりましたが、離婚後も定期的に子供と面会交流をしていました。しかし、急に子供と会えなくなり、事情を確認すると、母親からの虐待により子供が児童相談所に保護されたことがわかりました。
Aさんは、母親に状況を問い合わせましたが、要領を得なかったことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。当事務所では、Aさんのご希望をお聞きし、最終的には親権者の変更を求めることにしました。
そこで、速やかに親権者変更の調停を申し立て、児童相談所による保護事件の資料開示を求めたり、調査官調査の実施を求めた結果、裁判所の心証が親権者を変更するという心証になってきたことから、最終的には親権者を変更するという内容での調停が成立しました。
親権者の変更は、両当事者(両親)が同意すれば変更は可能ですが、親権者が応じない場合には、家庭裁判所の審判によることになります。
ただし、親権者の変更が認められるためには、一般的には、親権者を取り決めた当時の事情から変更があり、親権者の変更が子の福祉のために必要であることが必要なようです。親権者の変更は容易には認められませんが、虐待があるような事案では認められる可能性は比較的高いのではないかと考えられます。
約3年

Aさん
配偶者
Aさんは、配偶者と離婚しましたが、離婚した後でその元配偶者から、多額の扶養的財産分与を求める調停を申立てられました。Aさんは、対応が分からなかったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、元配偶者が、別居や離婚後に発生した病気などを理由に扶養的財産分与を求めていたことから、別居後に相当な金額の生活費を支払っていることと、婚姻や離婚と関係ない事情であること等を反論し、最終的には扶養的財産分与の請求は裁判所に認められず、解決されました。
通常の夫婦間で形成された財産を分ける財産分与とは別に、扶養的な財産分与が請求されることもあります。
どのような理由から扶養的な財産分与が認められるか、その理屈上の根拠が確定しているわけではありませんが、裁判例上は、一定の状況で一定の期間、扶養的な財産分与が認められる場合もあります。
約3年

依頼者:男性(元夫) 60代
相手方:女性(元妻) 60代
Aさんは、かなり前に別居し、ようやく離婚が成立したところで、離婚後になって元配偶者から財産分与を請求されました。
別居の時点がかなり前であったことから、別居時を財産分与の基準時点とすることで合意しましたが、基準時点の預金額の資料が取得できないなどの問題があり、また子供名義の財産が財産分与の対象になるか等の様々な論点が発生しました。
最終的には、元配偶者の財産を、裁判所の調査嘱託によって発見し、両当事者の財産額が概ね同じくらいであったことから、財産分与をしないという審判になりました。
約2年半
財産分与をする場合、一般的には別居時点を基準時点とすることが多いようです。
この場合、別居からかなり時間が経ってから離婚をすると、別居時点の財産の資料が取得できなくなっている場合がありますので、注意が必要でしょう。

依頼者:女性(妻) 30代
相手方:男性(夫) 30代
依頼者は、2年ほど前に離婚しましたが、財産分与をしていなかったため、時効完成前に元夫に対し、財産分与を請求するため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
時効が迫っていたことから、内容証明を送付して時効の完成を猶予したうえで、交渉を開始しました。
ただ、年金分割を行うことも視野に入れていたため、離婚から2年が経過する前に合意が成立しなければ、財産分与と年金分割の調停を申し立てることを決めていました。
交渉では、双方が財産を開示したうえで、短期間のうちに協議を重ね、結果としては、依頼者側の希望に沿った内容で合意することができました。
1か月間
本件では、特に相手方が協議での解決を強く希望していたため、依頼者に有利なかたちで短期間で解決できたと思っています。

依頼者:男性(元夫) 50代
相手方:女性(元妻) 50代
依頼者は、相手方に対して離婚調停を申立てましたが、財産分与についての話し合いが難航し調停が長期化したため、離婚することだけを優先して調停を成立させ、財産分与については、別途審判を申立てて解決を図ることにしました。
本件では、まず管轄の問題がありました。
相手方が離婚成立時点で他の管轄地に引っ越していたため、財産分与の調停であれば相手方の住所地が管轄となりますし、財産分与の審判であれば、依頼者の住所地を管轄とすることができました。
この点、依頼者の住所地を管轄とした方が何かと便利ですし、早期解決を図るためにも、調停ではなく最初から審判で扱ってもらうよう上申し、認めてもらうことができました。
また、本件は妻が家計を管理していたため、妻側に財産を開示してもらう必要がありましたが、妻側が財産の開示を拒んだため、調査嘱託により、多くの財産を開示させました。
しかし、財産がある程度明らかになっても、妻がほぼすべての財産について特有の主張をしました。
そのため、当方は、相手方の主張の一つ一つについて、矛盾点を指摘し、共有財産であることを主張していきました。
その結果、妻から夫に対し、予想を上回る額での財産の分与を命じる審判が出されました。
かかる審判に対しては、妻が即時抗告し、高裁のなかでも特有財産性が争いとなりました。
当方は、高裁でも相手方の主張一つ一つについて、矛盾点を指摘していきました。
結果として、高裁では、さらに原審を大きく上回る額での分与額が認められました。
3年間
相手方の主張を事細かに分析して、反論したことが功を奏したと感じています。
また、分かりやすい書面を心がけたことが、裁判官にも好印象を与えたと感じています。

依頼者:Aさん(夫・男性)
相手方:元妻
Aさんは、配偶者に頼まれて、配偶者の親の土地の上に、住宅ローンを組んで自宅を建てました。
しかし、Aさんと配偶者の仲が悪くなり、Aさんは自宅を出て別居することになりましたが、住宅ローンはそのまま支払い続けることになりました。
そうこうしているうちに、配偶者は、Aさんに対して婚姻費用分担調停を申し立てましたので、その対応と財産関係の整理のため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんの希望は、離婚して財産関係をすっきりさせることでしたので、当事務所では、婚姻費用調停に対して離婚調停を申し立て、離婚や財産の整理を求めました。
配偶者が多額の金銭請求をしたことから、話し合いが困難となり、婚姻費用調停を継続させつつ、離婚調停だけ不成立にして、離婚訴訟を提起しました。
結局、最終的には、配偶者に自宅の名義を変更し、住宅ローンは配偶者が支払うこととして、Aさんから配偶者に多少の解決金を支払うことで解決しました。
約1年間
配偶者の親や親族の所有する土地の上に、夫婦の一方が住宅ローンを借りて自宅を建てることは、よく行われています。
このような状態で夫婦の仲が悪くなりますと、自宅を建てた方(土地の所有者と血縁のない方)が家から出ていくこともよくあります。
このような場合、住宅ローンを貸した金融機関との関係では、自宅から出て行ってもローン返済の義務が残りますので、資金面で注意が必要です。
また、建物の所有者と土地の所有者が異なる場合には、不動産を誰がどのように取得するかなど、解決にかなり難航したり、解決しないこともありますので、この点も注意が必要です。

依頼者:Aさん(夫・男性)
相手方:元妻
Aさんは、養育費を公正証書で取り決め、離婚しましたが、離婚後、妻との間で口頭で養育費減額の合意をしていました。
しかし、それを書面化していませんでした。何年かしてから急に、元妻から養育費の未払いがあると言って、公正証書を使ってAさんの給与を差し押さえてきました。
そのためAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、相手が差し押さえをしている以上、話し合いで解決することは困難だと考え、請求異議の裁判を速やかに提起し、差し押さえ金額が増加してきた段階で不当利得返還請求に切り替え、訴訟を継続しました。
本人尋問まで行った結果、裁判官から口頭での養育費減額があったと言う心証が開示されましたので、最終的には差押えを取り下げ、養育費は減額後の合意どおり支払うという和解ができました。
約1年間
養育費を公正証書で取り決めた場合、いきなり給与の差し押さえなどの強制執行手続きをされることがあります。
養育費の減額を口頭で約束したとしても、それを後で証明できるかは何とも言えないところがありますので、減額する際にはきちんと記録の残る方法で減額を取り決めた方がいいでしょう。

依頼者:Aさん(妻 会社員)
相手方:Bさん(夫 会社員)
子供:長女(20代)、次女(20代)
婚姻期間:30年
Aさんは、裁判で配偶者と離婚しましたが、離婚が成立した後で、元配偶者から財産分与の調停を申し立てられ、対応のご相談にいらっしゃいました。
自宅が共有財産ではなく特有財産(元配偶者の受け取った遺産)であったため、居住の問題もあわせて解決するよう交渉し、一定の財産分与と引き換えに一定期間、自宅に居住する権利を確認して、解決しました。
約2年間
離婚すると財産分与があわせて問題になることがあります。。
財産分与は離婚してから2年間が時効であるため、何らかの事情で離婚の際に財産分与も一緒に解決できなかった場合には、離婚後しばらくしてから財産分与を請求される可能性もあります。
例えば、離婚訴訟で、一方が離婚を拒否していた場合、判決で離婚が認められることがありますが、財産分与が争点になっていなければその裁判では判断されず、財産分与が後に残ってしまう場合があります。

依頼者:Aさん(夫・男性)
相手方:Bさん(妻・女性)
Aさんは、離婚した際に公正証書で子の養育費を取り決めていましたが、転職による減収で支払いが難しくなったため、元配偶者に養育費の減額を相談しました。
しかし、減額について話ができなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
養育費の減額について、当事者間の話ができない場合、早めに減額調停を申し立てた方がいいことから、調停を申し立て、並行して話し合いを試みました。
当初に取り決めた養育費額が、標準的な金額より高額であったこともあり、話し合いがつかず、最終的には裁判所の決定で、Aさんの減収、元配偶者の収入の増加、当初の養育費額といった要素を考慮し、養育費額がある程度減額されることになりました。
約1年間
一度取り決めた養育費も、収入の増減といった事情の変更があれば、増減額が認められることがあります。
話し合いをすることも考えられますが、一般的な考えでは、裁判所に調停を申し立てた時点から変更されると解釈されていますので、養育費の増減額を求める場合には、早めに調停を申し立てた方が無難な場合もあります。

依頼者:Aさん(夫・50代男性)
相手方:Bさん(妻・40代女性)
子ども:小学生2人
Aさんは、妻との離婚を希望して弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、妻が高圧的なため、当事者間での話し合いが困難とのことで、弊所に離婚協議の代理をご依頼されました。
本件では、住宅ローンが残った自宅があり、その評価が問題となりました。別居後、かかる自宅に妻と子らが居住しており、自宅を取得することを希望している妻側としては、自宅の評価を低くした方が有利なため、露骨に低く評価した査定書を提出してきました。
そのため、当方は、かかる査定書の問題点を指摘し、当方が考える適正な評価額を主張しました。
自宅の評価については、双方の意見が完全に一致することはありませんでしたが、相手方も歩み寄り、他の財産も併せて調整することで、全体として合意に至ることができました。
不動産の評価が問題となる事案で、業者に低めもしくは高めに査定書を作成してもらい、その査定書を検証することなくそのまま提出してくるケースが見受けられます。
しかしそういった極端な評価をした査定書は、かえって信用性を失い不利益な結果となることがありますので注意が必要だということを改めて感じた事案でした。
9か月

依頼者:男性 Mさん 会社員
相手方:元妻
Mさんは、妻との関係が悪くなって別居しました。その後、離婚することになりましたが、離婚する時点では財産分与に関して取り決めをしませんでした。
離婚した後、元妻から財産分与の調停を申し立てられ、裁判所から呼出状が届いたため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
調停では、裁判所から、まずは別居した時点の財産の資料を提出して、別居時点の財産を記載した目録を作成してほしいと指示されました。
しかし、Mさんは、結婚前の仕事で一定の預貯金があり、結婚前の預貯金の相当部分が、結婚後の生命保険の保険料に支払われていたり、生活費に支払われていました。
そこで、結婚前の預貯金は、別居時点の預貯金額から差し引いて差額のみ分与対象とすべきと主張したり、結婚時の預貯金から保険料を支払った生命保険の返戻金は分与対象とすべきではないと主張したり、結婚時点の預貯金を同居中の生活費に使った部分は分与対象額から控除すべきと主張するなど、様々な主張をしました。
元妻は、このような主張を全く認めなかったことから、調停での話はつかず、審判を経て即時抗告まで争い、結果としては、一定範囲でMさんの主張が認められ、元妻の請求額からは大きく減額された額で決定されました。
財産分与は、離婚の際に取り決めなければ、離婚から2年間は請求することができます。そのため、離婚してもいきなり財産分与を求められることがありますので、注意が必要です。
また、財産分与は、一般的に、離婚前に別居している際には、別居時点に存在した財産を基準にすることが多いと思われます。
結婚前からある財産があれば、その分は対象から外れるという主張をしなければ、別居時点の財産で判断されることになる可能性が高く、難しい立証活動をしなければならない場合が少なくないでしょう。
2年

依頼者:男性 30代男性 Aさん 会社員
相手方:女性 30代女性
子ども:2人(相手方と同居)
Aさんは3年前に相手方と調停離婚し、お子さまたちの養育費として一人当たり月2.5万円を支払っていました。しかし、転職に伴い、取り決め時より年収が大幅に減ったことから、養育費減額のご相談にいらっしゃいました。
受任後、相手方の戸籍を調べたところ、相手方が離婚後まもなく再婚し、再婚相手とお子さまたちが養子縁組を組まれたことが判明しました。これを理由に、養育費の支払免除を求めて、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることにしました。もっとも、相手方はAさんに現在の住所を知られないよう、相手方が支援措置を申し出ており、職権によっても相手方の住所地は開示されなかったため、初動は難航しました。
このままでは、調停の場で話し合いをすることができません。そこで、裁判所と市役所と協議した結果、以下のような取り扱いとしました。
このようにすることで、相手方の住所をAさんに知られることなく、かつ、Aさんの調停を申し立てる権利も保障されることになります。
結局、遠方の裁判所が管轄となり、無事相手方に調停申立書が届けられ、調停を行うことができました。遠方だったため、電話会議で調停が行われました。調停自体は一回で成立し、過去の判例にしたがい、養育費は0円に減額されました。
支援措置は、本来であれば(元)配偶者からのDV等の被害から身を守るための制度であり、有益な制度であることに間違いはありません。しかし、実際にそのような危険がない場合でも、手続次第では支援措置が認められてしまう場合はあります。
本件は、支援措置を継続しなければならない場面か、疑問が残る事案でした。これにより、正当な権利主張も認められないのでは、かえって不公平を生じさせます。多くの自治体と裁判所を巻き込みながらも、最終的には希望を叶えることができました。
半年

Aさん 40代 男性 医師
妻:40代 会社員
子ども:3人
Aさんの妻は仕事で週の半分以上は県外で過ごしており、お互いに多忙な中ですれ違うことが増え、夫婦喧嘩をすることが多くなりました。
その後、妻が2人の子を連れて家を出て完全に別居状態になり、ほぼ同時に妻が代理人を立てて離婚を求めてきました。当初、Aさんが直接妻の代理人と交渉していましたが、交渉が難航してきたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
受任時点で妻には代理人がついていましたので、Aさんと相談してこちらの希望をまとめ交渉しました。
当初、妻は多額の財産分与を求めてきましたが、Aさんの財産を整理していくと、妻が思っているような財産はなさそうでしたので、離婚を円滑にかつ素早く行うために、現在の財産についてはそれぞれの名義に帰属させたままとする形で合意が成立しました。
また、3人のお子さんについては、別居時点で上の子がAさん、下の子たちは妻のもとで生活をしていましたので、それを維持して親権をとりきめたうえで、Aさんが養育費を支払うことで合意し、協議離婚が成立しました
本件のように時間をかけて財産開示をしても十分な財産分与が見込めない事案では、離婚を優先させるのであれば厳格に財産開示をせずに早期に終了させるというのも手です。
本件は、妻としては財産よりもとにかく離婚したいという気持ちが強い事案でしたので、かかる手段が有効だったと思います。
半年

Cさん 30代 男性 会社員
元妻:30代 職業不明
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)
Cさんは、協議離婚の際に面会交流の条件を取り決め、約1年間、子どもと面会交流を行っていました。 しかし、元妻が再婚後、面会交流を拒否するようになり、話し合いに応じなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。
元妻の現在の戸籍と住所を調査し、面会交流調停を申し立てました。
元妻は当初、再婚相手との新しい家庭を築くために、子どもの写真を送るといった間接的面会交流を希望してきましたが、子の福祉と利益のために、直接的面会交流は行われることになりました。
期日間に試行的面会交流を行いながら、調停で条件について話し合いを行いました。
結果として、面会交流の頻度、時間、受渡場所、連絡方法、およびプレゼントの頻度などを具体的に取り決め、調停が成立しました。
親権者となった親が再婚したことをきっかけに面会交流を拒否されるケースはまま見られます。しかし、子どもにとっては、同居する養父が父親であると同時に、実父も大切な父親です。本件でも、子どもたちはもともと実父との面会を楽しんでおり、試行的面会交流でCさんと再会したときもとても喜んでいました。調停を通じて、面会交流が子供たちのためのものでもあることを元妻に認識させることができたのが良かったと思います。
1年

Aさん 女性 会社員
Aさんは、夫の親との対立、子育てに対する夫の非協力などから、結婚生活に耐えられなくなり、離婚を考え、ご相談にいらっしゃいました。
離婚調停を申し立て、子どもを連れて別居を開始しました。
調停で話し合いを進める中で、夫も離婚に合意することとなりました。
結果として、未成年者の親権者をAさんとすること、養育費として、相当額に加えて子どもが専門学校を卒業するまでの学費を考慮した金額を夫が支払うこと、相当額の財産分与を夫が支払うこと、年金分割の按分割合を0.5とすることで合意し、調停離婚が成立しました。
調停中、夫の態度が二転三転し、調停委員から調停の取下げを提案されるなど、なかなかうまく進まない場面もありましたが、具体的な条件を提示し、今離婚した方が思わせることで調停を成立させることができました。本件のように相手方が離婚に難色を示す場合、調停の取下げを勧められることがありますが、安易に取り下げるのではなく、毅然とした対応が必要です。
1年2か月

Aさん 男性
Aさんは、妻と離婚したのですが、離婚することしか決まらず、その他の問題は未解決のままでした。離婚後、元妻から財産分与調停を起こされたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
事前に財産内容や財産を形成した経過を確認し、資料をそろえた上で調停に臨み、Aさんの自宅の土地を相続によって取得したことと、建物部分にはローンが多く残っていること、元妻には貯蓄型の保険があること等を主張し、財産分与するものがない等の主張をしたところ、財産分与を相互に請求しないという内容での調停が成立しました。
離婚の際に決める必要がある事柄は、未成年の子がいる場合の親権者のみです。逆に言えば、財産分与や慰謝料、養育費などは、離婚と同時に決めることも可能ですが、決めずに離婚だけすることも可能です。代理人を入れずに夫婦で直接話し合って協議離婚をする場合に、離婚の条件は決めず、離婚だけすることもあると思われます。
そういった場合には、離婚後一定期間内であれば、財産分与等を別途決めることも可能です。しかし、資料の準備などが大変になりますので、この点は注意が必要です。
約3か月

Aさん 40代 女性 会社員
元夫:40代 会社員
婚姻期間 6年
子ども:2人
Aさんは、13年位前に、養育費の取り決めを公正証書に作成して、協議離婚をしました。
元夫からの養育費の支払いは3~4年はありましたが、一度支払いが止まってしまいました。連絡を取って、支払いをお願いしたところ、一旦は支払いがありましたが、そのうち連絡が取れなくなってしまいました。
この間に元夫が自己破産をしたことがわかりました。
元夫の連絡先がわからず、どのようにしたら養育費を払ってもらえるか、ご相談にいらっしゃいました。
元夫の住所を明らかにすることから始まります。
幸いにも元夫の就業先は把握しています。
元夫に公正証書を送達し、その送達証明を付けて、強制執行の申立をしました。
その後、3年に渡り、元夫の勤務先から養育費分の支払いを受けることができ、自己破産前に発生している分も含めて請求していた全額を回収することができました。
この事件のように、請求債権が全額回収できることは一般的にはなかなか困難です。相手方も転職してしまえば、転職先の給与に対して、新たに強制執行の申立をしなければ回収することができなくなります。転職先を探し出すことは時間も要しますし、大変な作業です。今回は、幸いにも元夫が3年間転職しなかったので、回収ができた事件でした。
約3年4か月

Dさん 40代 男性 会社員
元妻:40代 パート・無職
婚姻期間 10~15年
子ども:2人(未成年)
Dさんは、妻から離婚調停を申し立てられ、財産分与、慰謝料、面会交流以外の調停が成立し、離婚しました。
財産分与について、お互いの主張が対立したため、財産分与調停が別途申し立てられましたが、不成立で審判に移行したため、ご相談にいらっしゃいました。
妻の特有財産と主張する預貯金が共有財産であること、Dさんの預貯金の基準日を別居時残高とすることを主張し、不動産の見積り、自動車の査定額を立証しました。
結果として、審判手続内で、要求額よりも大幅に減額された財産分与をDさんが行うことで合意し、解決しました。
約4か月

Eさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート・無職
婚姻期間 20~25年
子ども:2人
Eさんは、財産分与と養育費の取り決めをしないまま、協議離婚をしましたが、妻や子どもとまだ同居していました。
妻の代理人弁護士から、財産分与と養育費の条件が提示されたため、ご相談にいらっしゃいました。
共有財産である不動産からEさんが退去すること、不動産を妻が取得する代わりに妻から財産分与を行うことなどを、妻の代理人は提示してきました。
しかし、不動産の時価から、ローン残額、リフォーム代、売却時諸費用、妻の親族からの贈与分を差し引くと、分与額は数千円であるという主張でした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を行いました。
結果として、早期解決のための減額はあったものの、相当額の財産分与を一括で支払ってもらうこと、算定基準額よりも減額された養育費をEさんが支払うことで、合意書を作成し解決しました。
妻の代理人が当初提示した離婚条件が法律的に通らないということを指摘することによって、妻側提示の条件が改善され、最終的に良い解決ができました。もし、Eさんに代理人がつかなかったら、Eさんにとって不利な結論になったと思われます。
双方の代理人が2~3日に1回程度電話連絡をし合い、早期解決のためには、迅速な対応が極めて重要であるということを改めて感じました。
約3か月

Dさん 女性 20代 会社員
夫: 30代 会社員
婚姻期間 約1年
子ども:1人
Dさんは結婚以来、夫のEさんが浪費に頭を悩ませていました。Dさんは貯蓄の案を出すなどして改善に努力しましたがEさんは浪費を止めませんでした。
それどころか、生活費に困ったDさんは両親に生活費の援助をしてもらい、出産費用も全て負担するに至り、将来に対する不安は決定的なものとなり、Dさんは離婚を決意して生後間もない子供と共に自宅を出て別居を開始しました。
別居後の話し合いの結果、Eさんが離婚届に署名したため、Dさんは速やかに離婚を届け出ました。しかしその後、Eさんが代理人をつけて、養育費及び面会交流の協議を求めてきた為、Dさんは解決のためにご相談に来られました。
Dさんからの依頼を受けて、当事務所はEさんが依頼した代理人弁護士と交渉を開始しました。
養育費についてEさんは当初、毎月2万円もしくは一括400万円を支払うと提示していましたが交渉の結果、毎月4万円に増額することができました。
また面会交流の条件についても、基本的にDさんの付き添いの下での面会とする等Dさんの希望に大筋で沿った条件で合意がまとまり、「養育費及び面会交流に関する協議書」を作成し、その後公正証書も作成して解決終了いたしました。
本件は生まれたばかりのお子さんが女の子であったため、父親のEさんとの面会条件について、母親であるDさんの付き添いを条件とするDさんの強い要望がありました。そのため3歳以降の面会交流では、Dさんの付き添いを拒むEさんとの条件交渉のために、弊所弁護士は相手方代理人と何度も協議を行いました。
面会交流の調停等裁判手続きは、調査官の調査が入ることから解決までに時間がかかるケースが多く、親子共々負担となります。本件が交渉で解決できて大変良かったと思います。
約6か月

Cさん 30代 男性 会社員
妻:30代 パート
婚姻期間:5~10年(別居期間3年)
子ども:1人
Cさんと妻は、以前から同居と別居を繰り返していました。
別居期間が3年近くなり、離婚の話も始まりましたが、Cさん名義のマンションのローンや養育費などの問題で双方の要望がかみ合わなかったため、ご相談にいらっしゃいました。
Cさんが住宅ローンを支払うマンションに妻と子が住んでいたため、生活費からの交渉になりましたが、ローンの支払いを考慮した生活費額で取り決めをしました。
また、離婚の際には養育費の額とマンションをどうするかが問題になりましたが、公正証書で取り決めることと引き換えに低めの養育費額で取り決め、マンションも妻が残ローンを負担した上、マンションの名義を変更する代わりに代償金をCさんに支払うとの合意ができ、比較的速やかに協議離婚で解決しました。
6か月

Bさん 30代 男性 会社員
妻:20代 パート
婚姻期間10~15年
子ども:2人
妻は子どもが生まれて間もなく育児を放棄し、Bさんが仕事をやめて育児をする期間もありました。
妻が子どもに暴言・暴力をふるうため、子どもは2人とも精神状態が不安定になりました。
さらに、妻が家庭を放棄したことにより、子どもの親権者をBさんとして離婚しました。
離婚後、突然、妻が代理人をつけて面会交流調停及び親権者変更調停を申し立ててきたため、ご相談にいらっしゃいました。
Bさんは、妻の虐待により妻との面会が子どものストレスになるとして、面会交流と親権者変更を拒みました。
妻側は虐待ではなく躾だったと主張し、双方の意見のくい違いが大きく、歩み寄りが難しい状態となり、調停が不成立となりました。
調査官調査を裁判所に求めたり、調査に立ち会うなどして、調査をした結果、妻による暴言・暴力の存在が認められ、離婚後は子どもたちも精神的に落ち着いてきたことが調査結果として出され、結果として、親権者変更の申し立ては却下されました。
また、面会交流についても、子どもの福祉に反するものとして認められず、直接の面会交流や、妻から子どもへの連絡は認められませんでした。
1年1か月

Aさん 40代 女性 パート
夫:40代 会社役員
婚姻期間:15~20年
子ども:なし
Aさんは家庭内別居の状態だった夫からの要求で離婚しましたが、慰謝料はなく、貯金の半分と車1台の使用権を取得しました。
夫婦の実質共有財産がほかにもあるはずとのことで、財産分与および年金分割に関するご相談をお受けしました。
夫にも代理人弁護士がつき、財産を開示され、離婚協議書を作成しました。
交渉の結果として、Aさんの要求に近い金額を財産分与として夫から受け取ることができ、車の名義変更、年金分割が行われました。
6か月

離婚をするにあたり、また離婚した後も、未成年の子どもに関することは重要な問題です。
親権は父、母のいずれに決めるか
面会交流の方法、頻度、連絡方法をどのように決めるか
ただでさえ、夫婦の関係がよくないため離婚する(した)わけで、双方が勝手な意見を言い合ってしまうものです。
子どもが健やかな成長を遂げるために、できるだけ悪影響を与えまいとするのが子の福祉における基本的な考えです。
つまり、子どもにとって不利益とならないように、父と母は配慮し話合いをするべきです。
また、子どもは、父と母の話合いに対して、自分の意見を表明して、手続きに参加する権利があります。
父親、母親どちらかに対しても、目の前にしている親を立てた思いや考えを話すのが子どもです。
調停になった場合、裁判所は、子どもの思いや考えを聞く機会を設け、調査官調査を行います。
「調査官」という中立な立場の職員が、親抜きで子どもに実際はどう思っているか話を聞きます。
それだけでは十分ではない場合もあります。
子どもがほんとうはどう思っているのか、ある程度の年齢になれば、自分の考えをもっと聞いてほしいと思うのではないでしょうか。
こんな事例がありました。
面会交流調停において、監護している親の代理人が、子どもの年齢等を考慮し、子どものために子どもの手続き代理人選任を提案しました。
その提案に、非監護(監護していない)親の代理人も了承したため、裁判所は、子どもをこの面会交流調停に職権参加させ、国選の手続き代理人を選任しました。
これにより、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続きの中に届けることができました。
また、別の事例です。
親権者宅で生活していたのですが、そこの家を出て非親権者宅で生活していた子ども自ら、弁護士会の子ども相談窓口に電話をかけてきました。
「現在、親権者変更の審判をしていて、調査官調査の調査官に自分の気持ちを伝えたが、心配なので、自分にできることはないか。」 という相談でした。
その話を聞いた担当弁護士は、私選の子どもの手続き代理人として、この親権者変更の審判に利害関係参加許可を申立て、許可されました。
子どもの意見や気持ちを掬い取ることができ、子どもにとって良い結果になったのではないでしょうか。
参考までに

離婚調停で面会方法が成立調書の中に定められました。
しばらくは定められた面会交流を実施しました。
しかし、ある時点から実施されなくなり、母側から、面会交流調停を起こされました。
このケースは面会をなくしたい調停です。
父母の離婚調停において、調査官の調査を受けた中学生の子どもが、自ら弁護士による相談窓口に電話をかけて、 担当した弁護士に、不安な気持ちや進路について、打ち明けたそうです。
この弁護士を、「子の手続き代理人」に選任し、父母の離婚調停に利害関係人として参加許可の申立てを行いました。
子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で届けることにより、子どもに寄り添った結果を導き出すことができるのでしょう。

家庭裁判所では、離婚するときに未成年の子どもについて、 子どもの親権者を父母のどちらかに決めるか、 別居している親と子どもの面会に関する条件をどう決めるか、 などの手続が行われています。
これらの手続は父母の間で取り決められますが、決められたことは子どもにとって大きな影響を与えることになります。
そのため、子ども自身が「自分の意見を聞いてほしい。」と思うこともあるでしょう。
また、子どもと一緒に暮らしていない親からすると、「子どもがどう思っているのか?」、「子どもの本心を知りたい。」と思うこともあるでしょう。
一方、子どもと一緒に暮らしている親からすると、「子どもが自分に気兼ねして本当の気持ちを話せていないのではないか?」、あるいは、「子どもは本心を話しているのに、 相手に信じてもらえないのではないか?」など、不安に思うこともあるでしょう。
そのようなとき、子どもが家庭裁判所の手続に参加でき、子どものための代理人弁護士を選んでもらうことができる「子どもの手続代理人」という制度があります。
子どもの手続代理人は、父母どちらの味方でもなく、あくまでも子どもだけの代理人として、子どもに寄り添って、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で届けます。
子どもは、父母が何についてどのような手続をしているのかよく分からないまま、不安に感じていることも多くあります。子どもの手続代理人は、父母が行っている手続の内容や、 子どもが手続に参加するに当たって必要な情報、子どもの生活に関する情報を、子どもに分かりやすい言葉で説明し、子どもの相談に乗ったり、子どもに寄り添いながら一緒に考えたりします。
その上で、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で届けます。
このように、子どもの手続代理人は、子どもが手続に参加して自分の意見を表明する権利(子どもの意見表明権、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)12条)を守り、 実現するお手伝いをします。
<参考>
※ 外務省の「児童の権利に関する条約」全文のページはこちら
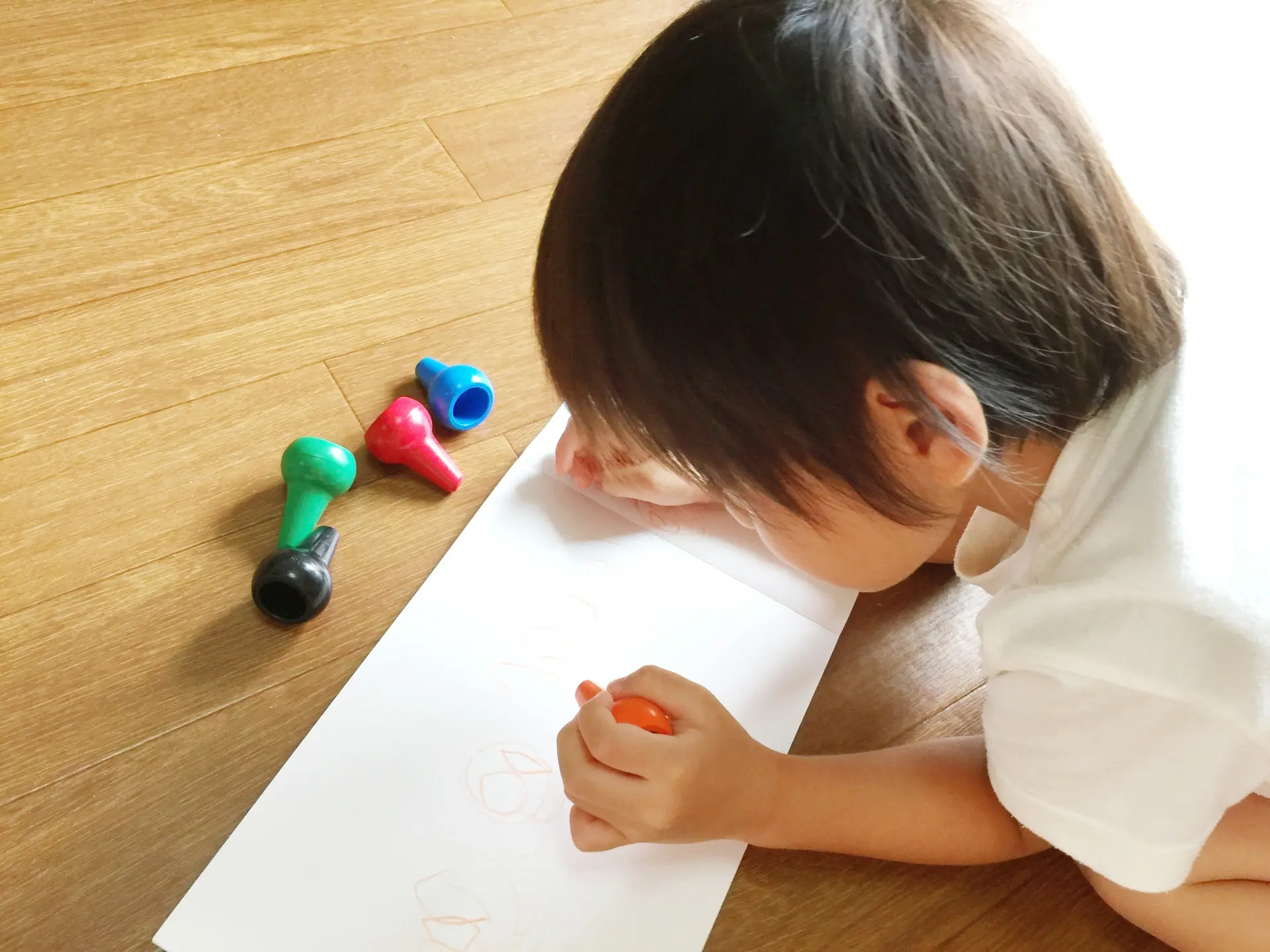
子どもの手続代理人は、具体的には、次のような活動を行います。
子どもと面談して、子どものことをよく知り、子どもの疑問に丁寧に答えて、子どもが自分の意見を伝えやすい関係を作ります。
子どもが自分の意見を決めたら、書面などで裁判所に伝えるとともに、家庭裁判所の手続期日に出席して、必要に応じて子どもの意見を説明します。
子どもの気持ちを尊重しつつ、これまでの家庭裁判所の手続の経過を踏まえて、子どもの手続代理人から、子どもの利益を中心とした調停案を提案することもあります。
家庭裁判所の手続が行われた後には、子どもにその内容を分かりやすく説明し、子どもの疑問にも答えます。
こうした活動に当たっては、父母に協力をお願いする場合もあります。

子どもの手続代理人を担当した弁護士の費用(報酬)は、多くの場合、子どもは支払うことができないので、父母が支払うこととされています。
家庭裁判所の手続が終了したら、裁判所が子どもの手続代理人の報酬額を決定しますので、裁判所の決定に従って父母が報酬を支払うことになります。
父母が経済的理由から費用を負担することが難しい場合は、子どもが日本弁護士連合会(日弁連)の「子どもに対する法律援助」を利用することもできます。「子どもに対する法律援助」を利用した場合、子どもは費用を負担する必要がありません。
<参考>
日弁連の「法律援助事業」のページへのこちら (「子どもに対する法律援助」は、日弁連の「法律援助事業」の一つです。)現在、家庭裁判所で離婚、面会交流などの手続をされていて、子どもの手続代理人が必要かもしれないとお考えの方は、手続を依頼している代理人弁護士がいれば、 その弁護士にご相談ください。
依頼している代理人弁護士がいないなど、相談する弁護士がいない場合は、愛知県弁護士会 法律相談センターが実施している子どもの人権相談でご相談ください (相談料は無料です。相談方法など、詳しくは、リンク先をご覧ください。)。
年度の変わり目は、実は離婚の多い季節でもあります。
母子家庭かどうかは、保育園や幼稚園入所の優先順位にも関わってきますので、そのことも関係しているようです。
お子さんのいる方が離婚をする際、よく考える必要があるのは公的扶助、いわゆる母子手当の問題です。
一人で子供を育てていくのは大変です。
母子手当は、いつ、いくらもらえるのかについて、今回は見ていきましょう。
母子家庭または父子家庭など、夫婦の一方または双方から養育を受けられない児童のための手当です。
平成22年8月1日 から、父子家庭も児童扶養手当支給の対象となりました。
児童扶養手当の満額受給額は以下のようになっています。
受給年齢は18歳に到達して最初の3月31日(年度末) までです。
ただし、満額受給には所得制限があり、受給資格者の所得が満額受給の限度額以上の場合、児童扶養手当の額は10円単位で減少していき、一部支給の限度額を上回ると児童扶養手当を受給することはできなくなります。
所得額は以下の計算式で算出され、児童1人の場合の満額支給の限度額は57万円です。
【前年所得 (給与所得控除後) + 養育費の8割 – 各種控除額】
一部支給(9,780円〜4万1,420円)の額は、別の計算式で算出されます。
ジョイナス・ナゴヤ (母子家庭等就業支援センター名古屋市相談室) のホームページで試算ができますので、ご自分がどれだけ受け取れるか、試算されてみてはいかがでしょうか。
愛知県遺児手当の満額受給額は、児童1人につき月額 4,500円、受給期間は18歳の3月末までの5年間です。
※3年目までの受給額は4,500円ですが、4・5年目は2,250円と減ってしまいます
こちらも満額受給には所得制限があり、その所得額は、扶養親族が一人の場合230万円です。
名古屋市にお住まいの場合、名古屋市の扶助制度としてひとり親家庭手当というものがあります。
こちらは、18歳の3月末まで3年間受給できるものです。
満額受給の所得制限の額は、57万円です。
1の児童扶養手当は、児童手当と名前は似ていますが、全く別物です。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日に達するまで(分かりにくい言い方ですが、「中学校修了前まで」と読み替えてください)の子供がいる家庭であれば原則受け取ることのできる手当です。
| 3歳未満の場合 | 月額1万5,000円支給 |
| 3歳から小学生の場合 |
|
| 中学生の場合 | 月額1万円支給 |
所得制限は以下が限度額です。
所得制限以上の世帯でも、月額5,000円は受給することができます。
以下では、イメージがわきやすいように具体例でみていきましょう。
名古屋市に住んでいる夫婦 (5歳の子が一人) が離婚し、母親 (給与所得控除後の所得120万円、養育費受取なし)が子供を引き取る場合を考えます。
| 児童扶養手当受給額 | 月額3万1,360円 |
| 愛知県遺児手当 | 月額4,500円 |
| ひとり親家庭手当 | 月額9,000円 |
| 児童手当 | 月額1万円 |
| 合計:月額 5万4,860円 |
合計で、かなり大きな金額になりますよね。
愛知県遺児手当、ひとり親家庭手当はそれぞれ5年、3年と受給期間が限定されています。 しかし、児童扶養手当は18歳の3月末まで継続して受給できますので、請求時期が遅れれば遅れるほど、受け取ることのできる額が減ってしまいます。
離婚の際は、このような公的扶助のことも十分考慮して今後の生活のプランを立てましょう。

テレビドラマや漫画などで、登場人物にお金が必要になった時、本の間やタンスの奥から出てくるもの、それがヘソクリですね。
これを読まれている皆さんの中にも、へそくりを貯めていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
自分が稼いだお金から天引きしているんだから、自分のお小遣いからこっそり貯めたんだから、自分のものに決まってる、と思いがちですが、実は法的にはそうではありません。
一方の配偶者(夫または妻)にその存在が知られているかどうかにかかわらず、婚姻期間中に、夫婦の協力に基づいて形成した財産は、原則として夫婦共有財産となります。
そのため、離婚の際の財産分与においては、一方がこっそり貯めたへそくりであっても分与の対象になってしまうのです。
この2点を比較していただければ分かりやすいかと思います。
1の場合、お小遣い以外の残高は夫婦共有の口座に残り、夫婦共同生活(子どもの教育費、家具・家電の購入など)のために使われたはずです。
ところが、2の場合、本来夫婦共有財産となるはずのお金が、たまたまあなたにお小遣いとして多めに支払われていたために、30万円をあなたの手元に残すことができたのです。
へそくりというのは本来夫婦共同生活のために使われるはずであった夫婦共有財産が、たまたま一方の手元にあるという状態にすぎないのです。
例外的に、夫婦の一方の親が亡くなった場合の相続財産をへそくりとして貯めていた場合、そのへそくりは夫婦の協力によって得られたものではありませんので特有財産として財産分与の対象とはなりません。
へそくりが誰のものであるかを決めるポイントは、今あなたの手元にあるかどうかではなく、「へそくりの出所がどこか?」によって決まってくるということですね。
財産分与について詳しくはこちら

離婚をお考えの方は、いつ弁護士に相談に行こうと考えるのでしょうか?
浮気が見つかった!大きなけんかをした!といったきっかけもあるかもしれません。
または、時期的なものというのもあると思います。
例えば、年の後半になってくると「年内に離婚したい」という方がいらっしゃいます。
年内に何かしらのめどを立てたい。年内にすっきりして新しい年を迎えたい。
そんなお気持ちは理解できますね。
また、年度が変わるぐらいのタイミングでご相談に来られる方のお話を聞いていますと、「年度内に離婚したい」と考えている方が結構いらっしゃるように思います。
この年度内というのは、子どものことが大きく関係しています。
子どもがいると、離婚に伴い、子どもの姓を変える、引っ越しをするため転校をする、ということが生じる方もいると思います。
子どもの学校生活を考え、新学期から新しい環境に少しでもスムーズに移行したい、と考えてのことですね。
ここで残念なのが、離婚が成立するには時間がかかる場合があるということです。
協議でスムーズに解決することもありますが、場合によっては数年離婚に至らないというケースもあります。
それでは間に合わない!と落胆される方もいるかもしれません。
れでも今、まずは弁護士に相談してほしいと思います。
年度内に離婚というのは難しいかもしれませんが、今後の見通しを立てるというのはとても大切だと思います。
一度弁護士にご相談をしてみてください。
仕事から帰ってきてみたら、『もう、あなたとは生活していけないので実家に帰ります。離婚してください。』との書き置きを残して、妻が荷物をまとめて家を出ていっていました。
家のことは妻に任せきりにしていたため、私は、パソコンのパスワードも通帳の場所もわからず、日々の炊事洗濯にも困る状態です。
私が困ることをわかっていて何も言わずに出て行った妻の行動は、悪意の遺棄じゃないですか?
法律相談で、このような質問を受けることがあります。
この事例で、妻が裁判で離婚を求めた場合、妻の上記行動が悪意の遺棄になるでしょうか?

正当な理由なく、同居、協力義務を履行しないことをいいます。
正当な理由がある場合、すなわち合意による別居や病気療養中であるための別居などの同居拒否は「遺棄」にあたりません。
悪意の遺棄だと裁判所に認められると、妻からの離婚請求は「有責配偶者からの離婚請求」ということになり、離婚が認められるハードルは上がります。
そのため、もし、夫が妻と離婚したくない場合には、悪意の遺棄を主張しなければなりません。
また、妻としては悪意の遺棄と言われては困るため、上記のような出て行き方をすることは避けなければなりません。
そのためにも悪意の遺棄にあたるか否かは重要な観点です。
では、冒頭の事例は悪意の遺棄にあたるでしょうか?
結論から言うと、冒頭の事例は悪意の遺棄とは言いがたいと思われます。
まずは、感触をつかんでいただくために悪意の遺棄の代表的な判例をご紹介しましょう。
浦和地判昭和60年11月29日 置き去りが認められた事案
夫が半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続けた。
判決要旨
夫は半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないから、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当する。
名古屋地判昭和49年10月1日 置き去りが否定された事案
夫が妻に行先を告げず突然家出して消息を断った事案。
判決要旨
妻に行先を告げず突然家出して消息を断った夫は、正当な理由なく妻との同居義務及び協力扶助義務を尽くさないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認め得ない。
冒頭の家出した妻も以下の理由から正当理由が認められそうです。
では、置き去りにされたこと自体が離婚原因に全くならないかというと、そんなことはありません。
民法770条1項2号の「悪意の遺棄」まではいかなくても、770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められる可能性はあります。
以下では、悪意の遺棄は認められなかったが、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められた例をご紹介しましょう。
大阪地裁昭和43年6月27日 あまりに多い出張、生活費を入れなかった事案
夫が仕事の出張などで一ヶ月の大半を家庭外で過ごし、しかも生活費をほとんど入れないまま8年近くが経った。
判決要旨
夫がたとい仕事のためとはいえ、余りに多い出張、外泊等家族を顧みない行動により、妻に対する夫としての同居協力扶助義務の義務を十分に尽くさなかったことをもって今直ちに原告に対する「悪意の遺棄」に当たるとするにはやや足りないけれども、なお「婚姻を継続しがたい重大事由」があるとするに十分であり、その責任の過半が夫にあることもまた明らかである。
横浜地裁昭和50年9月11日 妻が実家に帰ったまま戻ってこなくなった事案
病気療養のため実家に戻った妻が、家に戻るよう説得に来た夫や夫の両親に罵詈雑言を浴びせた。
判決要旨
妻の両親及び妻が夫を罵詈雑言したのに、夫らに対し謝罪する意思が全くなく、妻は夫らを責めるのみで自己を反省しようとは全くせず、これにより夫は右のような妻と共同生活をすることが不可能となり、両者の婚姻関係は回復しがたいまでに破綻したということができ、右に至った責任は夫側にないことは明らかであり、それに双方の年齢、婚姻継続期間、子どもはいないこと等を考慮すれば、夫には婚姻を継続しがたい重大な事由がある。
このように、悪意の遺棄は認められなくても、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとされることがあります。
悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由の有無など民法上の離婚原因は、判断が難しい点ではありますが、裁判で離婚をする際には必要となるため、自分にはどれがあるのか、どれなら裁判で認められるかを、慎重に判断することが重要です。
裁判での離婚に必要な理由について詳しくはこちら
配偶者に不貞行為をされた方が相談に来られるとき、配偶者または不貞相手への慰謝料請求をするかどうかという話になりますし、不貞行為をしてしまった方が相談に来られるときは、どのくらい慰謝料を請求されてしまうのか、不貞相手にも慰謝料請求がなされるのか等をご相談されます。
その際、慰謝料請求だけではなく、不貞行為をした配偶者又は不貞相手の職場に不貞をしたことを言いたい、あるいは言われてしまったということがしばしばあります。
このような人は、職場に伝えることによって、不貞行為をした配偶者または不貞相手が職場をクビにされる、または少なくとも職場に居づらくさせたいという、いわゆる「仕返し」を目的としていると思われます。
不貞行為をされて許せないという気持ちは、よく分かります。 しかし、その気持ちは不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟で慰藉されるべきものであって、職場に不貞行為を伝えることは単なる嫌がらせでしかありません。
それどころか、職場に伝えたことを不法行為として、伝えた側に対して損害賠償請求をされることがあります。
配偶者に不貞行為をされた夫が不貞相手に損害賠償を求めた本訴に対し、不貞相手が職場へ不貞行為を暴露されたことについて夫に対し損害賠償請求の反訴を提起した事案において、夫の代理人が、不貞相手の代理人から職場へ不貞行為を伝えないよう警告されていたにもかかわらず、不貞行為を不貞相手の職場に暴露し、不貞相手が退職した。
判決要旨
(不貞行為を勤務先に暴露して慰謝料の支払いを求めるなどの、)このような(弁護士の)交渉の態様は、社会常識に裏打ちされた合理的な対話を進めるものとはいい難く、許容範囲を超えるものというべきである。…正当な理由なくこれ(不貞行為についての法的紛争を抱えていること)を第三者に開示する行為は、プライバシーを侵害するもの又は弁護士法23条に違反するものとして、不法行為になるものと解するのが相当である。
東京地裁平成24年12月21日(事件番号平成23年(ワ)第25471号、同29716号)
その損害の範囲には、慰謝料だけでなく、逸失利益、すなわち不貞相手が仕事を辞めさせられなければ得ていたであろう6か月分の収入及び弁護士費用も含められ、結論として損害額は193万円に上りました。
この事例では認められませんでしたが、場合によっては、職場に不貞行為を伝えることが名誉棄損となる恐れもあります。
このように、不貞行為を配偶者または不貞相手の職場に伝えることは、伝えた側が損害賠償請求をされてしまう危険性のある行為ですので、不貞行為をされてしまった場合には、配偶者または不貞相手に対する慰謝料請求という正当な法的手段によって対処し、くれぐれも嫌がらせのために職場に不貞行為を暴露することなどないようにして下さい。
不倫慰謝料請求について詳しくはこちら
令和元年12月23日、養育費の算定に関する司法研究の研究報告が公表されました。
この司法研究は、従前の養育費・婚姻費用に関する算定表の公開から15年が経過していることを踏まえ、より算定表を現在の社会実態を反映したものとするためなされたものです。
具体的には、子ども2人(いずれも0~14歳)で義務者の給与が年550万円、権利者の給与が年100万円であった場合、従前の算定表よると、養育費は月6~8万円であったのに対し、新しく公表された算定表によると月8~10万円となっており、全体的に義務者の負担が月1~2万円程度増額したものとなっています。
したがって、令和元年12月23日以降は、上述の例の場合、2万円程度多く養育費がもらえることとなります。
そこで、本稿では、従前の算定表に基づき今回公表された算定表より低い養育費をもらっている場合、増額を求めることができるのかをご説明します。
結論から申し上げますと、養育費算定表の改定を理由として、増額を求めることはできません。
養育費の増額を求める場合には、事情の変更があったことが必要となります。
算定表の改定は、養育費の額を変更すべき事情の変更には該当しないと司法研究の概要に明示されており、これにより増額を求めることは困難であるといえます。
しかし、算定表の改定の他に、事情の変更に該当する事実があった場合には、増額を求めることができます。
具体的には、以下のような場合に増額を求めることができます。
養育費の増額を求めることは、一度決定した養育費を変更するものであり、養育費を当初決定するときより難易度の高い交渉となります。
また、権利者に生じた養育費を増額したい理由が、養育費の増額を請求し得る事情の変更にあたるのかは専門的な知見に基づく判断が必要となります。
したがって、養育費の増額を求めたいと考えた場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
※こちらの記事は2020年6月5日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
新型コロナウイルス感染防止と面会交流の実施に関する見解が法務省民事局から示されました。
同見解によると、新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現在の状況下では、従前取り決められた方法で面会交流を実施すると、子供の安全確保が困難になる場合も生じ得る。
そのような場合には、面会交流の方法の変更を検討する必要がある。
方法の変更について、父母間で話合いができる場合には、子供の安全確保を最大限に配慮し、面会交流の方法について父母間で話し合う。
これまで、直接会う形での面会交流を実施していた場合でも、子供の安全に配慮し、一定期間、通信機器等を用いた交流を検討することが考えられ、その際には、次の事項について話合いをすることが考えられる。
父母間で話合いをすることが困難な場合には、無理に当事者間で話し合おうとせず、必要に応じて弁護士等の専門家に相談するようにしてください。
詳しくは法務省HP
お子さまへの新型コロナウイルス感染を防止する点から面会交流実施の見合わせや、方法の変更を検討されている監護親、親権者の方は多くいらっしゃると思います。
もっとも、非監護親や非親権者が面会交流の実施を強く要求したり、方法の変更を強く拒み、父母間で話し合いが困難なことも多いと思います。
このような場合に、専門家である弁護士に依頼すると、弁護士により問題点が整理され、代替方法の提案や一定期間の面会交流の見合わせの合意を獲得するなどし、面会交流の条件について調整できる場合があります。
弊所では、感染防止のための様々な対策をしておりますので、安心してご相談ください。
弊所の感染対策について詳しくはこちら
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)