本当は離婚したいのに離婚に踏み切れない理由として、離婚後の生活に強い不安を覚えるという点を挙げる方が多いようです。
たしかに、離婚すれば、もう夫婦ではなくなりますから、自分の生活は自分ひとりの力で支えなければなりませんし、家事や育児を夫婦で分担するということもできなくなります。
しかし、離婚後の生活に対する漠然とした不安を抱えたまま、いつまでも不満を募らせたまま結婚生活を続けることは必ずしも良い選択とはいえないでしょう。
そこで、今回は離婚後の生活に関する様々な不安を解消するための方策について解説したいと思います。

特に専業主婦・主夫の配偶者と離婚した人は離婚後の家事の負担を思い知らされるでしょう。
婚姻中にほとんど家事をしたこともない人は、離婚する前に、一度離婚後の家事について良く考えるようにしておきましょう。
また、同じように婚姻中、ほとんど育児をしてこなかった人が未成年の子の親権者となり育児をする場合も同様です。
他方、婚姻中に主として育児をしてきた人でも、離婚後は全て一人での育児になります。
特に、離婚後は家計を支えるために婚姻中より多くの時間を仕事に費やさなければならない場合もありますから、その場合の仕事と家事・育児のバランスのとり方については十分に考えておくべきでしょう。
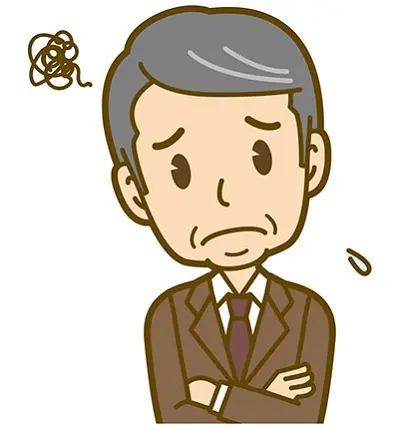
離婚はそれまでの辛い婚姻生活から解放される喜びであることも多いでしょうが、逆に精神的に負の要因にもなり得ます。
離婚によるパートナーの喪失は悲しみと絶望感を残すことがあり、離婚後はしばらく不安定な精神状態に追い込まれることがあります。
また、婚姻生活を軸として形成された人間関係が一変して強い孤独を感じることもあります。
さらに、離婚後の新生活に向けてこなさなけばならない様々な雑務が更に追い打ちを掛け、焦燥感に襲われることもあります。
このように離婚後の精神状態は離婚前に想像していたものとは違い、非常にネガティブなものになる可能性のあることを忘れてはいけません。
ですから、離婚前に、離婚後の精神衛生を保つ手段を考えておくことは非常に有益なことだといえます。

人によっては周囲の人に離婚したことを言いたくない、隠したいと思われるでしょう。
しかし、離婚後の生活では婚姻中には感じなかった強い不安やストレスを感じることもあるでしょうから、身近に離婚したことを打ち明け親身になって相談を聞いてくれる友人を作っておくべきでしょう。
離婚したことを言い出せないために一人で悩み事を抱えたままでいると精神を病んでしまう危険すらあります。

離婚後に新しいパートナーに巡り合い再婚を考えることもあるでしょう。
その場合には、再婚禁止期間の存在に注意しましょう。
女性は離婚して100日を経過しなければ再婚できないことになっています。
この再婚禁止期間は子の父親が前の夫の子なのか、新しい夫の子なのか、分からなくなるのを防ぐための制度です。
そのため、男性の場合は再婚禁止期間の制限はなく離婚してすぐに再婚できます。
離婚後の生活面でのマイナス点は離婚前には想像もしていなかったようなものであることがあります。
ですから、離婚する前に必ず離婚した後の生活を想像した上、少しでもマイナス点を解消できるための方法を事前に考えておくようにしましょう。
また、離婚後の再婚について女性には再婚禁止期間がありますから、離婚前から交際していたパートナーと離婚後に再婚する場合には注意しましょう。
離婚は単なる婚姻関係の解消を意味するものではなく、実際には社会生活や精神面において大きな影響を与えるものですから、離婚について不安や悩みを抱えている場合には、ひとりで悩まないで弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
12月2日 名古屋家庭裁判所にて、財産分与調停申立事件について家事調停を申し立てました。
12月4日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申し立てました。
12月12日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申し立てました。
12月13日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申し立てました。
11月5日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
11月5日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
11月5日 千葉家庭裁判所松戸支部にて、離婚等請求事件について判決が出ました。
11月7日 名古屋家庭裁判所にて、離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
11月7日 名古屋高等裁判所にて、即時抗告申立事件について即時抗告を申立てました。
11月14日 名古屋家庭裁判所にて、請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件について審判が出ました。
11月21日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
11月29日 京都家庭裁判所にて、離婚請求事件について裁判上の和解が成立しました。
10月1日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
10月1日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
10月1日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
10月2日 名古屋家庭裁判所にて、子の監護者指定調停申立事件について調停が成立しました。
10月2日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
10月3日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
10月3日 名古屋家庭裁判所にて、離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
10月3日 名古屋高等裁判所にて、即時抗告申立事件について特別抗告を申立てました。
10月7日 名古屋家庭裁判所にて、請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件について家事審判を申立てました。
10月8日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、財産分与審判申立事件について家事審判を申立てました。
10月11日 名古屋家庭裁判所にて、請求すべき按分割合に関する処分申立事件について審判が出ました。
10月15日 名古屋家庭裁判所にて、請求すべき按分割合に関する処分申立事件について審判が出ました。
10月24日 岐阜家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
10月25日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。
10月31日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担申立事件について審判が出ました。
9月5日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、婚姻費用分担調停費用について審判が出ました。
9月5日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、婚姻費用分担調停費用について審判が出ました。
9月19日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停事件について調停が成立しました。
9月19日 名古屋地方裁判所岡崎にて、慰謝料請求事件について民事訴訟を提起しました。
9月20日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
9月24日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
9月24日 名古屋家庭裁判所にて、子の監護者指定審判申立事件について家事審判を申立てました。
9月24日 名古屋家庭裁判所にて、審判前の保全処分申立事件について保全処分を申立てました。
9月30日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
9月30日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
8月7日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等請求事件について裁判上の和解が成立しました。
8月7日 名古屋家庭裁判所にて、損害賠償等請求事件について裁判上の和解が成立しました。
8月8日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
8月9日 名古屋地方裁判所にて、慰謝料等請求事件について決定が出ました。
8月19日 福岡家庭裁判所にて、面会交流審判に対する抗告事件について決定が出ました。
8月28日 名古屋家庭裁判所にて、間接強制申立事件について申立てました。
7月10日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、婚姻費用分担調停申立事件にかかる調停が成立しました。
7月11日に名古屋高等裁判所にて、財産分与審判に対する即時抗告事件について即時抗告の棄却についての決定が出ました。
7月11日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、離婚請求事件にかかる裁判上の和解が成立しました。
7月12日に名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
7月12日に名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
7月12日に名古屋家庭裁判所にて、年金分割にかかる処分申立事件について審判が出ました。
7月19日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
7月25日に名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件にかかる調停が成立しました。
7月30日に名古屋地方裁判所にて、和解金請求事件にかかる和解が成立しました。
7月31日に名古屋地方裁判所にて、損害賠償等請求事件について民事訴訟を提起しました。
6月4日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
6月7日に名古屋家庭裁判所半田市部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
6月10日に名古屋家庭裁判所半田支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
6月11日に名古屋家庭裁判所半田支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。
6月14日に名古屋高等裁判所にて、養育費(増額)審判、同申立て却下審判に対する即時抗告事件について決定が出ました。
6月18日に名古屋家庭裁判所に面会交流調停申立事件について家事調停を申立てました。
6月21日に名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
6月21日に名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
6月24日に横浜家庭裁判所に養育費減額請求調停申立事件について家事調停を申立てました。
6月28日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
5月10日に名古屋家庭裁判所にて、離婚請求事件について裁判上の和解が成立しました。
5月21日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
5月22日に名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
5月24日に名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。
5月28日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
5月31日に名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。
4月25日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。
4月26日に名古屋家庭裁判所にて、面会交流審判事件について審判が出ました。
3月7日に名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担申立事件について審判が出ました。
3月12日に名古屋家庭裁判所半田支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。
3月12日に名古屋家庭裁判所半田支部にて、面会交流調停申立事件について調停が成立しました。
3月18日に名古屋地方裁判所にて、慰謝料等請求事件について裁判上の和解が成立しました。
3月25日に名古屋家庭裁判所に離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
3月25日に名古屋地方裁判所に慰謝料等請求事件について民事訴訟を提起しました。
2月6日 名古屋家庭裁判所半田支部に面会交流調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月13日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について調停が成立しました。
2月14日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月14日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月15日 名古屋地方裁判所に慰謝料等請求事件について民事訴訟を提起しました。
2月22日 名古屋家庭裁判所に離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。
2月26日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月26日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月26日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月26日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月26日 名古屋高等裁判所にて、損害賠償請求上告受理申立事件について決定が出ました。
2月28日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月28日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。
2月28日 名古屋家庭裁判所にて、財産分与申立事件について審判が出ました。
1月15日 名古屋地方裁判所にて、慰謝料等請求事件について調停が成立しました。
1月18日 名古屋家庭裁判所にて、子の監護者の指定申立事件について調停が成立しました。
1月18日 名古屋家庭裁判所にて、子の引き渡し申立事件について調停が成立しました。
1月23日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流調停申立事件について家事調停を申立てました。
1月24日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整調停事件について調停が成立しました。
1月24日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、婚姻費用分担調停事件について調停が成立しました。
1月25日 離婚協議について裁判外の和解が成立しました。
1月25日 名古屋家庭裁判所にて、養育費増額申立事件について調停が成立しました。
開業医の離婚においては、医療法人の出資持分返還請求の問題が生じる可能性があります。具体的には、平成19年3月31日以前は出資持分のある社員の存在する医療法人の設立が認められており、そのような医療法人の定款には、「退社した社員は、その出資額に応じて、返還を請求することができる」との条項を置いていることが多く、離婚の際、妻又は夫が医療法人を退社することになり、それに伴い上記の定款の条項に基づき出資額の返還を請求することになるのです。
このような出資持分の返還請求に関して問題となるのは、その返還すべき金銭の額です。今回は、この開業医の離婚に特有の医療法人の出資持分返還請求について説明したいと思います。

たとえば、開業医の夫が総出資額3000万円のうち2000万円、その妻が1000万円を出資して医療法人を設立した後、離婚時の当該医療法人の保有する財産の総額は6億円である場合、離婚に伴い退社する妻に対して、いくらの出資持分を返還しなければならいのでしょう。
仮に、定款に「退社した社員は、出資額を限度に返還請求できる」と記載してあれば、設立の際に妻が出資した1000万円を返還すれば足りるでしょう。しかし、実際の定款には「出資額に応じて」と記載されています。
この点につき、実務では、原則として、このような定款の記載は、退社時の医療法人の財産の評価額に、同時点における総出資額中の退社する社員の出資額の占める割合を乗じた額を返還することを規定したものであると理解されます(最高裁平成22年4月8日判決参照)。
したがって、先ほどの例では、医療法人は、妻に対して、6億円×(1000万円÷3000万円)=2億円を返還しなければなりません。しかしながら、医療法人は財産の全てを現金あるいは預金として保有しているわけではなく、その一部は不動産や未回収の医療報酬債権などの形で保有しているため、通常、妻からの2億円の返還請求に応じることは困難であり、また、仮に応じるとすれば病院の経営に大きな悪影響を与えるおそれもあります。そのため、離婚に際して、この出資持分返還請求の問題を解決することができないため離婚問題が長期化してしまうおそれがあるのです。
当然のことながら出資持分のない医療法人においては出資持分返還請求の問題は生じません。そこで、出資持分のない医療法人に移行することは出資持分返還請求の問題を解決する策の1つとなります。
移行するためには、定款を変更する社員総会決議、所管税務署に対する届出等の手続きをとる必要があります。ちなみに、平成19年4月1日以降に設立された医療法人においては、そもそも出資持分のある医療法人の設立は認められていません。
出資持分返還請求の問題の具体的解決策の1つは、事前に定款を変更して社員の退社の際の出資持分の返還は出資額を限度とする旨の条項にすることです(このような医療法人は出資額限度法人といいます。)。
このような定款の変更により、出資持分の返還は、退社する社員の出資額を限度とすることになるので高額な返還を請求されることを回避することができます。但し、離婚の問題の発生した後、退社の見込まれる配偶者からの高額の出資持分返還請求を回避することだけを目的とした定款変更は、場合によっては、公序良俗違反等の理由から無効とされる可能性があるため注意しましょう。
出資持分のある医療法人のままの場合には、先に説明した出資額返還請求の問題は不可避となります。そのため、この問題を解決するには、当事者間の協議あるいは訴訟手続により、その返還額を決定するほかありません。
なお、上記の最高裁の判例では、原則として、返還額は出資割合に応じた額であるとしながら、具体的返還額については、当該医療法人の公益性を適切に評価し、出資者が受ける利益と当該医療法人及び地域社会が受ける損害を客観的に比較衡量、医療法人の資産形成の具体的経緯の諸事情を考慮して、出資割合に応じた全額の返還の請求を認めることが不当である場合には、権利の濫用等を理由として、その金額を制限する余地を認めています。
医師の離婚における財産分与においては、特に以下の点が問題となり得ます。

医師は高収入のため、その保有する財産は多種となり、その金額自体高額となる傾向にあります。
そのため、医師との離婚における財産分与では、何より、財産分与の対象となる財産を調査することから始まります。
特に離婚の危機の迫った時期以降は、離婚に伴う財産分与を意識して、保有財産を意図的に隠匿するおそれがあることから、同居している段階において、医師である配偶者の保有財産について意識してチェックしておきましょう。
また、財産といえば、通常、預金、不動産、自動車などの実用品であり価値の高い物を思い浮かべると思いますが、医師のような高所得者の場合には、実用品ではない骨董品、絵画等を所持しているような場合があり、そうした物は自動車や不動産等に匹敵するような極めて高額の価値を有していることもありますから注意しましょう。
開業医の場合には、病院・医療法人と医師個人の財産との混在により、財産分与対象財産であるかについて、明確に判断できないような場合があります。
たとえば、医師である配偶者が個人の財産を特定の時期から特に理由なく病院・医療法人名義の財産としているような場合には、このような財産は医師個人の財産とみなして、財産分与の対象とされることもあるでしょう。
開業医の夫と離婚する場合には、医療法人の出資分の払戻しの問題に注意が必要ですが、そもそも、医療法人の出資分の払戻しとは何でしょうか。
平成19年の医療法改正前は、出資持分のある社団医療法人の存在が認められていました。
要するに病院に出資することができました。
そして、このような出資持分のある医療法人の定款には、通常、社員資格の喪失時に出資者に対する出資額に応じた払戻しを認める記載がありました。
そのため、医師の夫と離婚して、出資持分のある医療法人の社員から退く妻であれば、出資分の払戻しを請求することができるのです。
問題は、払戻しの金額です。
定款には、「出資額の限度」ではなく、「出資額に応じて」と記載していますから、単純に1000万円出資した場合に1000万円を返還することでは足りません。
この払戻しの金額は、医療法人の資産総額×(払戻請求者の出資額÷全体の出資額)により算定されます。
たとえば、医療法人設立時、夫3000万円、妻1000万円の出資をしていた場合、離婚時の病院の資産総額が1億円の場合、払戻額は1億円×(1000万円÷4000万円)=2500万円になります。
どうして、このことが問題になるかといえば、病院の資産は現預金に限られないため、そもそも払戻額を準備できないこともありますし、計算通りの払戻しを行うと病院の経営が成り立たなくなる危険が生じうるためです。
そのため、開業医の夫と離婚する場合には、この医療法人の出資分の払戻しについて揉めるため、離婚問題は長期化することがあります。
実務では、財産分与における寄与割合は、個人の尊厳及び両性の本質的平等の観点から、原則として、2分の1として、特段の事情のある場合に限り、例外的に2分の1とは異なる割合での分与を認める傾向にあり、これは「2分の1ルール」と呼ばれています。
そして、実際のところ、財産分与において、2分の1ルールの修正を認めるケースは稀であり、ほとんどのケースでは2分の1の寄与割合により財産分与は行われています。
しかし、医師の離婚の場合には、この2分の1ルールの修正が認められるケースがあります。
これは、医師という職業が個人の努力や才能により獲得した資格による高度の専門的知識・技能を基礎とした職種であり、かつ、それゆえに多額の収入を得ているため、夫婦共同財産に対する寄与割合について、医師である配偶者の割合が他方の配偶者より大きいものと考えられる場合があるからです。
裁判例では、財産分与の寄与割合について、同様の趣旨から、医師である夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割として2分の1ルールを修正する判断を示しました。
もっとも、裁判所は、他方、妻が家事や育児だけでなく病院の経理を一部担当していた事情を考慮すれば、妻の寄与割合を4割より小さいものとすることは許容できないとの判断を示しています(大阪高等裁判所平成26年3月13日判決参照)。
このように、2分の1ルールの修正の可否及び修正の程度については、個別の事案における具体的事情を考慮して判断されるため、当事者としては自分にとって有利となる具体的事情を主張できようにしておきましょう。

開業医である配偶者は、自身の経営する病院において、他方配偶者を雇用していることがあります。この場合において、離婚を理由として他方配偶者を解雇することはできるでしょうか。

夫婦の問題と雇用の問題は別問題ですから、基本的には、離婚を理由として配偶者を解雇することはできません。
我が国において、使用者の解雇権は、いわゆる解雇権濫用法理に従い、その有効性は厳格に判断されるため、離婚という私的領域における事情を理由として、解雇を正当化することは困難です。
それでは、離婚の理由が他方配偶者の病院内での不倫の場合でも、これを理由とした解雇はできないのでしょうか。
職場内の不倫を理由とした解雇については、これを有効とした裁判例(長野地方裁判所昭和45年3月24日判決)と否定した裁判例(旭川地方裁判所平成元年12月27日判決)の双方が存在しています。
いずれの場合でも共通していることは、単なる不倫の事実だけでは解雇はできないということです。
観光バス会社の妻子ある運転手が、未成年の女性バスガイドと肉体関係を持ち、妊娠をさせたことが、勤務途中での同宿等の職場環境の特殊性から観光バス会社の社会的地位、名誉、信用を傷つけ、その業務の正常な運営を阻害した
ということを理由として、解雇を有効としたものがあります。
不倫により社内の風紀・秩序を乱した具体的事実についての証明がない
ということを理由として解雇を無効としたものがあります
このように、職場における不倫関係は、私生活上の行為であるため、原則として懲戒解雇の対象となりませんが、「会社の社会的評価に重大な悪影響与える」ような場合に限り、有効とされます。 そうすると、病院内での不倫を理由とした解雇の認められるのは、たとえば、看護師等の配偶者が病院内において複数の患者と不倫の関係を結び、これにより病院の評判を著しく毀損して患者数を激減させたなど極端な場合に限られるでしょう。
以上のとおり、開業医の経営する病院において配偶者が働いていた場合、離婚を理由として当該配偶者を解雇することは、かなり難しいという結論になります。そこで、解雇できない場合の対応について考えてみましょう。
一般の会社と同様、労働者を有効に解雇できないものの、その労働者には会社から離れて欲しいと考える場合の対応として考えられるのは、退職勧奨です。退職勧奨とは、要するに、使用者である開業医は一方的に労働者である配偶者を解雇することはできないので、当該配偶者の自発的意思に基づく退職を促すのです。
このとき、離婚の原因について明らかに配偶者の責任であるようなケースでは解雇はできないとしてもその責任を取るという意味での退職を促すことは、それほど難しくはないでしょう。
離婚に至った原因について、双方に責任のあるようなケースや明らかに開業医に責任のあるようなケースでは、無条件に退職してもらうよう促すことは難しく、たとえば、次の就職先を見つけたり、あるいは、次の就職先の見つかるまでの生活費用として、ある程度の金銭的給付を行ったりするなどの対応を必要とするでしょう。
なお、退職勧奨は、あくまでも退職という労働者の自発的意思を促す行為であるため、高圧的な態度や誹謗中傷に当たる言動や本人が拒否しているのに執拗に退職を迫るなどの行為は、不法行為と評価されることもあるので注意しましょう。
このような退職勧奨を行っても配偶者が退職に応じなければ、離婚後も従前どおり同じ職場において働かざるを得ないでしょう。
財産分与の対象になる財産とは?
財産分与の対象となる財産は、預貯金、給与、有価証券、不動産などです。
そして、その名義は共有でなくどちらか一方となっていても構いません。
実質的に夫婦が共同で築いた財産であれば名義のいかんに関わらず財産分与の対象となります。
 退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。
退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。
そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。
夫の給料から日々の生活に使用された後に残っていたものを預貯金すれば、それが財産分与の対象となるのと同様に、退職金も婚姻中に夫婦が協力し、二人の結婚生活において作り上げられた財産といえるからです。
退職金といえば、夫が汗水流し働いた結果の報いであるような印象も受けます。
しかし、夫が外で仕事に専念できたのは、妻のサポートがあってこそ、という考えがあるのです。

そもそも退職金とは、長年仕事に従事してきた人の労働の結果、支払われるものです。
つまり夫が長年仕事を頑張ってこれたのは、夫婦の協力があってこそ、妻が夫の身の回りの世話をし、育児を含む家事をこなし、仕事に支障を与えないような環境を整えていたと考えるのが妥当なのです。
その考えのもとでは、退職金も財産分与の対象となります。
離婚時、すでに支給されていた退職金は、財産分与の対象となり、退職金全額のうち、基本的に婚姻期間に応じた割合が対象となります。
例えば、勤務期間が20年間でそのうち婚姻期間が10年間という場合、退職金のうち半分が財産分与の対象となります。
ただ、気をつけなければならないのは、退職金相当額が残っているか否かという点です。退職金を受領したのがだいぶ前のことであって、離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないので、財産分与の対象にならないとされてしまう可能性が高いです。
まだ退職金が支払われていない場合、退職金が確実に支払われるかどうかは分かりません。
そこで、退職金が財産分与の対象とされるかは、退職金が支払われる可能性の有無で判断されます。
以下、いくつかポイントをあげてみます。
将来支給される退職金のうち、婚姻前の夫の労働により得られた部分は、財産分与の対象になりません。
具体的に財産分与の対象とされるのは、婚姻期間に応じた割合となります。
つまり、勤務期間が20歳から60歳までの40年間で退職金が2000万円の場合、婚姻期間が30歳か40歳までの10年間であれば、財産分与の対象となるのは一般的に2000万円全額ではなく、
2000万円×10年/40年=500万円と、計算されることが多いです。
もちろん、単純に1年の勤務に比例して退職金は増額するとは限らないため、実際には、退職金規程等を参照して、退職金の算定式を考慮し、財産分与の対象になる退職金の額を決めることもあります。
 退職金は、前述のとおり財産分与の対象になります。
退職金は、前述のとおり財産分与の対象になります。
退職金が、給料・賃金の後払い的性格を有し、退職金も二人の結婚生活において作り上げられた財産といえるからです。
但し、財産分与とは、結婚生活の中で形成された財産が対象になるということで、裁判所では、妻の寄与(貢献)は同居期間しか認められないとの考えが一般的であるため、別居時の時点で計算するのが原則です。そして、そのような期間に形成された財産について、妻は原則2分の1(0.5)の寄与があると推定されるのが一般的な裁判の考え方ですので、退職金について財産分与請求する場合は、おおよそ以下のような計算式となります。
<退職金財産分与の一般的な計算式>
| ( | 妻が夫の退職金について 請求する額 |
) | = | ( | 退職金支給額のうち 別居までの婚姻期間に対応する額 |
) | × | 0.5 |
ただし、これはあくまで一般的な計算方法ですので、妻の2分の1(0.5)の寄与については、事案によっては4割の寄与しかないと判断された事例もあります。
また、その支払い時期については、判例上いくつか考え方が示されており、支払い時期により退職金支給額の計算方法が異なります。
1.別居時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる額を基礎にする
簡単に言いますと、「今退職したら退職金はいくらになるか」を計算の基礎にする考え方です。
将来の退職金を受給できるかどうか不確実という考えにも対応できます。
2.将来受給する退職時見込額を中間利息を複利計算で控除して引き直した現在の価額を基礎にする
とても難しい表現ですが、簡単に言いますと、『将来受給する退職時見込額を基礎にはするが、「将来受け取るもの」を今受け取ることによる利息分を差し引く』ということです。
これら離婚時分与説には、まだ支給されていない分与金支払のための資金調達を強いることになるとともに、退職金が勤務先の倒産等により支払われなかった場合の問題を指摘する意見もみられます。
上記問題が生じないのは、次の考え方です。
1.将来の退職時に受給する見込額を基礎にする
2.離婚時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる退職金を基礎にしながら、将来の退職時の受給見込額が多くなることを考慮して、分与額の増額要素とする
離婚時に自己都合退職したと仮定した場合に受給できる退職金では少なくなるので、分与を受ける側の不利益を考慮した考え方です。
定年退職までの期間が短い場合には、将来の定年退職時に支給される退職金の額を基準とする場合が多く、定年退職までの期間が長い場合には、離婚時に自己都合退職した場合の退職金の額を基準にする場合が多いです。
もっとも、どちらの計算方法がとられるかについては、判断基準が明確にあるわけではなく、具体的事案に応じて判断されます。
このように、退職金を財産分与の対象にできるのか、また、その計算方法はどのようにすべきかといった問題は、専門的で複雑な判断となり事案によります。どのような主張・立証をして、どのような計算方法をとるべきかは、個別具体的なご事情によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

婚姻中、夫婦が共同生活の場所として自宅を取得した場合、清算的財産分与においては、基本的に他の財産と区別されることなく、夫婦財産の清算として処理されることになります。
そして、自宅の取得については、住宅ローンを利用する場合が多く、財産分与においては、自宅の評価額から住宅ローンの残額を控除した残額が清算対象となる財産とされます。離婚と住宅ローンについて詳しくはこちらをご覧ください。https://www.nagoyasogo-rikon.com/rikon-loan/
しかし、自宅は単なる財産ではなく、生活の拠点となる財産であるため、単なる財産の清算だけではなく離婚後の扶養の観点を考慮する必要があります。
財産分与は共有物分割とは異なるため、審判・判決により不動産を売却して売却代金につき分与割合に応じた支払を命じることはできません。
しかし、当事者双方の合意により自宅不動産を売却することは可能です。
その場合には、自宅不動産の評価額から住宅ローンの残額を控除した残額(住宅ローンが残っている場合)を夫婦の財産として清算することになるでしょう。
なお、その際の自宅不動産の評価における不動産業者の査定は、適正妥当な評価額の算定と実際に売却する際の不動産業者の選択に資するため複数の業者に依頼することを勧めます。
自宅不動産の評価額を住宅ローンの残額が上回る場合すなわちオーバーローンの場合には、当該自宅不動産は、実質的には負の財産であり、財産分与の対象にはならないものとされています。
もちろん、そのような場合でも当事者の合意により売却することは可能です。
しかし、オーバーローンの自宅不動産を売却する場合には、残ローンの支払という問題が生じます。
このとき、当然に残ローンを折半して負担することにはなりません。また、ローン支払中の自宅不動産には、抵当権が設定されていることが多く、売却した場合には、ローン会社から残ローンの一括請求を求められる場合があるので注意が必要です。
Q.オーバーローンのため財産分与の対象とならず、ローン、所有権ともに元夫である私名義の自宅があります。離婚後も元妻がこの自宅に住み続けていますが、私は何らかの請求ができますか。
A.この場合には、
自宅の査定方法としては、当事者間の合意があれば、固定資産評価額でも構わないとされています。
しかし、一般に固定資産評価額は低額となるため、代償金を取得する側が納得せず合意に至らない場合が多いでしょう。
無用な争いを避けるためには、複数の不動産業者の査定の平均を基準とする方法が考えられます。
自宅不動産の評価額を巡り対立が激しい場合には、相応の費用を負担して、不動産鑑定士による鑑定結果を基準とすることもあります。
なお、鑑定を利用する際には、鑑定費用の負担の問題や鑑定結果については異議を唱えないことを合意するなど事前に当事者間において協議しておくとよいでしょう。
自宅不動産を維持する場合には、その取得者と清算方法が問題となります。以下、場合分けして説明します。
住宅ローンの残っていない場合には居住を継続する配偶者に自宅不動産を取得させ、分与額との差額が生じる場合には、代償金を支払わせることで大きな問題は起きないでしょう。
たとえば、夫が住宅ローンの債務者であり、離婚後、妻は別の居住先を確保して生活することにして、夫は従前どおり自宅において生活するような場合には、夫に自宅不動産を取得させ、
自宅不動産評価額から住宅ローンの残額を控除した夫婦全体財産に分与割合を乗じた分与額を夫から妻に対して代償金として支払わせることになるでしょう。
なお、このときオーバーローンであれば、分与すべき財産はないため、夫から妻に対する金銭支払は生じません。
たとえば、夫が住宅ローンの債務者であり、離婚後、妻は子どもと従前どおり自宅において生活することにして、夫は別の居住先を確保して生活する場合には、妻に自宅不動産を取得させ、住宅ローン債務者を夫から妻に変更する方法や(もっとも、債務者の変更には債権者であるローン会社の承諾を必要とします。)、債務者はそのままにして実質的負担者は妻とする(夫名義の口座に妻がローン返済分を入金するなど。)方法が考えられます。
しかし、このような方法は、自宅不動産を取得する配偶者の代償金の支払やローン支払能力を前提としており、専業主婦(夫)のように、離婚後のローンの支払を期待できない場合には適切な方法とはいえません。
したがって、自宅不動産の居住を継続する配偶者の代償金の支払やローン負担を期待できないときには、住宅ローン債務者の居住しない不動産のローン返済の継続を十分期待できるような場合を除いて、
住宅ローン債務者に自宅不動産を取得させ、居住を継続する配偶者に対する自宅不動産の利用権(使用貸借権や賃借権など)を設定する方法により対応すべきでしょう。
なお、自宅不動産がオーバーローンの状態において、住宅ローンの債務者と居住を継続する配偶者とが異なるときに自宅不動産について居住を継続する配偶者に取得させるとすれば、
債務者である配偶者は居住しない不動産のローンを返済することになり、
他方、居住を継続する配偶者は特段の金銭負担なく自宅不動産を取得することになり極めて不公平な結果が生まれてしまいます。
そこで、そのような場合には、自宅不動産を取得する配偶者との内部的関係としてローン返済の負担の合意や他の財産の給付を求めるなどの対応を必要とします。
財産分与を理由とする自宅不動産の所有者の名義変更は夫婦間の合意に基づいて登記の申請することにより可能です。
しかし、住宅ローン会社との契約上、名義変更に債権者の承諾を必要としていることが多く、債権者である金融機関が、名義変更を承諾してくれる可能性は極めて低いでしょう。
そこで、名義変更するためには、親等からお金を借入れ、金融機関に一括返済したうえで、親に債務を返済していく等の方法をとることになります。
なお、離婚を強く望むため、妻が自宅に住み続けることを認めると共に夫がローンを支払い続け完済した時に名義も妻に変更するという条件を提案する男性相談者が一定割合おられます。
このような解決は、妻から見ても夫がローンの支払いを怠った場合には抵当権が実行されてしまいますし、住宅ローン約款に基づき、自宅を第三者に処分した場合には期限の利益を失い、一括返済しなければならなくなってしまう場合もあります。
また、通常離婚時の財産分与には贈与税がかからない扱いがされているところ、離婚後長期間経過後の名義変更には贈与税が課される危険がありますのでご注意ください。名義変更の手続について詳しくはこちらをご覧ください。https://www.nagoyasogo-rikon.com/procedure-after-divorce/name/

海外でも面会交流は子どもの福祉・利益の観点から重要であるとの認識から、これを積極的に肯定する傾向にあるようです。以下、海外の面会交流についてみてみましょう。
海外では、離婚後の親権について、共同監護の制度を取っている国も多いようです。これは、日本の場合、離婚後の未成年の子の親権は、必ず一方の親の単独親権とされているのとは異なり、共同監護という方式を選択できる制度です。共同監護には、子供が等しい時間を双方の親それぞれと生活する方法と一緒に生活する主たる養育者を決めたうえで、他方の親が積極的にかかわっていく方法があるようです。
そして、主たる養育者ではない親に対して、裁判所は子どもの最善の利益にとって有害でない限り、相当な面会交流の権利を与えなければならないとされており、その実態は日本における面会交流の判断より、かなり広汎に面会交流を認めるものであり、その禁止は、よほどの事情でない限り認められないようです。
ただ、共同監護の制度にすれば面会交流がスムーズにいくわけではなく、それを支える支援制度も整える必要があります。
面会交流を実施するためには、まず、その具体的内容を決定しなければならないところ、そのような合意は当事者間のみの話し合いではなかなか決められないこともあります。アメリカでは、そのような事態に直面した父母に対して家庭裁判所が養育計画の作成を支援するプログラムを実施する制度が整備されています。また、同様の制度は、イギリス、ドイツ、フランスなどの国にも存在しています。
たとえば、アメリカのカリフォルニア州では、基本的に離婚するには裁判所の手続きによる必要があり、子のいる夫婦が離婚する場合には、子の監護や面会交流について定めた詳細な養育計画を裁判所に示さなければならないようです。そして、これらの養育計画が作れない夫婦のための支援も整備されているようです。
なお、日本の家庭裁判所でも面会交流に関する調停を実施する前に父母に面会交流の意義・趣旨を理解してもらうためにDVDを鑑賞してもらうことがありますが、あくまでも調停という裁判手続上でのサポートであり、日本国内における面会交流に関する裁判外での自主的解決を支援するための公的サポートは未整備の状況です。
離婚した夫婦がいがみ合っていて、面会交流がスムーズにできない場合があるのは、日本も海外も変わりません。
そのため、合意した面会交流を具体的に実施するために面会交流の監督や中立的立場での子どもの引き渡しを担う第三者機関の存在が充実している国もあるようです。
アメリカでは、面会交流の仲介を担う有料の機関や無料のボランティア機関が存在し、親に問題がある場合には、家庭裁判所が積極的にその選定に関わり、また、介在する第三者の任務遂行に関する行動基準の策定を行うなどの支援を実施しています。
また、イギリスでは、当事者間の合意あるいは裁判所による決定に従った実際の面会交流の実施を支援するため「子ども交流センター全国協会」という機関が存在しており、
面会交流において第三者の介入を必要とする場合には中立公平の第三者として子の受け渡し、面会交流の監督などの役割を担い、面会交流の実施についての支援を行っています。
アメリカでは家族の法律に関する問題は各州の管轄であり、面会交流に関する各種支援の制度を運営するための費用は、
原則として、運営主体である各州あるいは関係する民間団体、当事者の負担とされていたところ、1990年頃から各州の面会交流の支援制度に対して連邦政府から助成金が支給されるようになりました。
このように海外では、面会交流は子どもの利益のためという趣旨を具体的に実現するため、いくつかの公的支援の制度が存在しています。
もちろん、そうした制度でも何らかの問題点はあるでしょうが、未だそのような制度が十分に整備されていない日本としては、そうした既に存在する海外の面会交流に関する支援制度を参考にすることになるでしょう。

本裁判例は,妻(B)及び夫(A)との子である長女(D)が,Aとその不貞相手(C)に対して,慰謝料を請求した事案です。
昭和45年,BはDを産んだ後,Aとの性交渉を持つことを嫌がるようになった。
昭和52年夏ころ,AはCと交際を始め,ほどなく肉体関係を持つようになった。
昭和55年ころ,BはAとCとの関係を知り,Aを非難したため,ACの関係解消。BはCから慰謝料100万円受領した。
昭和60年ころ,AはCとの交際を再開し,肉体関係を持つようになった。
平成元年10月ころ,Bは,A・Dとともに家族でアメリカに観光旅行
上記まで両者離婚の申し入れ等をしたこともなかった
平成6年3月26日,AはBに何も告げず,突然,Cとともにオーストラリアに出国し,駆け落ちした。それ以降,別居が継続。
本裁判例において,A・Cは,Bは昭和45年ころからAとの性交渉を拒むようになり,AとCとの関係が明るみに出た昭和55年以降は一切性交渉を持とうとしなかったこと等から,
AとCの交際が再開した昭和60年ころにはAとBの婚姻関係はすでに破綻していたため,不法行為責任を負わないとの主張をしました。
しかし,裁判所は,
「そもそも,婚姻は,男女の性的結合を含む全人格的な人間としての結合関係であり,その結合の内容,態様は多種多様にわたるものであって,性交渉の不存在の事実のみで当然に婚姻関係が破綻するというものではなく,破綻の有無を認定するにあたっては,夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要がある。」
との一般論を述べた上,上記事実関係からすると,破綻どころか,むしろ円満ともいえる通常の婚姻生活を営んでいたことが認められることから,
AとCは不法行為責任を免れることはできないとの判示をしました。
一般に,不貞行為に対する慰謝料請求の場合に,慰謝料請求を受けた側から,不貞行為があったことは認めるが,その時点で,夫婦間の婚姻関係が既に破綻していたため,不法行為責任は認められないという主張をすることはよくあります。もっとも,この「破綻」の判断をどのようにするかについては,裁判例上,統一的な基準はありません。
この点,本裁判例では,一般論として,破綻の有無は,夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要があると述べました。これには2つの意味があるといえます。
まず,破綻の有無は客観的に評価するという点です。これは,当事者の主観(婚姻関係継続の意思が一方になかった等)では判断しないとの意味を持ちます。
また,夫婦間の関係全体から判断するという点です。単に性交渉がなかったから破綻していると判断するのではなく,
別居の有無・期間等,
夫婦関係の悪化の程度,
子の有無,
離婚に向けた行動等
様々な事情を総合的に考慮して,婚姻関係の修復が著しく困難な程度に至っているのかどうか判断されるとの意味を持ちます。
以上述べたように,統一的な基準があるわけではなく,上記のことに鑑みると,不貞行為時点で夫婦間の婚姻関係が既に破綻していたと主張するのであれば,不貞行為前の事情で,婚姻関係が修復不可能だったことを基礎づける事実を,様々主張・立証する必要があると考えられます。
もっとも,この主張は,慰謝料額がゼロか百かの判断を求めることとなるため,認められることはあまり多くないと考えた方がよいです。
裁判例では,破綻までは認められないものの,関係が希薄であった,破綻寸前であった等評価して,慰謝料額を低額としたものも多く,個々の事案に応じた妥当な結論となるように判断しているといえます。

昭和58年12月,原告と原告の夫(A)が婚姻。夫婦関係は円満であったが,子はいなかった。
平成13年初春頃,インターネットを介してAと被告が知り合う
Aは,被告に対し,自分は妻がおり夫婦仲は円満であるが,子がなく,後継ぎがほしいと考えるようになったので,未婚の母となってくれる女性を探していることなどを伝え,生活費の支給を条件に婚外の男女関係を持つことを提案した。
被告は,かねてより子がほしいとの思いが強かったこともあって,Aの提案に興味を抱いたが,いったんは通常の結婚をして家庭に入る途を選択した方がよいと考え直した。そこで,平成13年6月20日,Aにその意向を伝えた。
これに対して,Aは,被告が迷いを払拭できるまで待つ意向であることを告げ,また,被告との関係が継続する限り経済的責任を持つこと,子が出生した場合,自己の生涯にわたり経済的援助を行うことを伝えた。被告は,このAからの勧めを受けて,上京して同人との婚外子を設けることを決意し,そのことをAに伝えた。
その後,被告は,Aからの融資金300万円を資本金として会社を設立し,同社の取締役に就任した。また,被告は,平成13年9月からは,Aが所有していた都内のマンションに居住するようになり,そこでAとの肉体関係を継続した。平成14年4月には,被告はAとの子を妊娠したため,Aに伝えたところ,Aは子を胎児認知した。
平成14年7月頃,原告は,知人からAに交際相手の女性が存在する可能性を示唆された。そこで,Aのパソコンのデータを調べたところ,Aと被告との不貞行為の経緯や同年4月に被告の妊娠が判明したことなどを知った。原告は,これらに強い衝撃を受け,Aに対し強い怒り,嫌悪を感じて,別居するようになった。
①被告が不貞行為を決意するに至るまでの経過においては,Aが主導的役割を果たしたことは否定し難いものの,被告は,結局はAの提案を受け入れ,Aからの融資金で会社の設立・取締役就任を果たし,Aとの肉体関係を継続して子を出産し,以後もAに生計を依存しているのであり,このように解消困難で恒久的な不貞関係の形成,継続に加担した点で被告の責任は軽視し難いものがあること,
②①に起因してAとの約19年に及ぶ婚姻関係の破綻を余儀なくされた原告の精神的苦痛は想像に難くないこと等の事情を考慮すると,慰謝料額は300万円が相当である
と判示しました。一般的に,婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素として考慮されており,婚姻期間が短い場合には減額要素として考慮され,婚姻期間が長い場合には増額要素として考慮される傾向にあります。
これは,不貞行為をした者に慰謝料が請求できるのは,
婚姻関係のある夫婦には平穏な夫婦生活を送るという利益を有しており,不貞行為により,
その利益を害した行為が不法行為として評価されることが根拠となっているところ,
平穏な夫婦生活というのは,婚姻関係が長く続くほど安定して強固になっていくため,婚姻関係が長いほど平穏な夫婦生活をより保護すべきと考えられているからであると考えられています。
本件では,被告とAの不貞行為によって,約19年に及ぶ婚姻関係の破綻を余儀なくされた原告の精神的苦痛は非常に重いと判断し,そのような結果に至った原因となる不貞行為について,Aが主導的だったとしても,被告の責任は軽減されないとして,一般的な相場より高いも300万円という慰謝料額を認定したものと思われます。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)